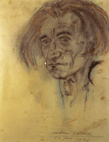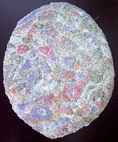|
はじめに 一. 障害者芸術運動の問題点 二. 西洋と日本における障害者芸術観 三. 障害者芸術運動の具合的事例 四 障害の他者性と表現の可能性 おわりに |
|||||||||||
|
はじめに 芸術の歴史的文脈や概念の中に、障害を持つ人々(1)の表現をどう位置づけるのか。この問題に向き合うことによって、障害者をめぐる社会的認識と芸術観を再考する契機を得られる。障害者の表現は、社会的不利益に芸術がどう貢献するのかという視点のみならず、現代の多様化する表現に対し何をもって芸術とみなすかという根本的な問いを投げかけるものである。 優生思想による断種や堕胎(2)によって、障害者の生を圧倒的に否定している力が障害者の連帯を作り上げてきた。日本において1990年代から障害者をめぐる社会意識に芸術表現がアプローチする動向が起こる。ひとつは、障害そのものを前に押しだし社会的不利益を意識化させる方向。もうひとつは芸術を手段とし社会的包容力を拡大しながら差別意識を乗り越えようとする方向である。本論は日本の障害者芸術運動の問題点と(一)、西洋と日本における歴史的背景の違いからその要因を明らかにし(二)、具合的事例によって障害者芸術の認識を再構築する糸口を求め(三)、障害の他者性と芸術表現の可能性について考察する(四)。 障害者という概念は、世界保健機構(WHO)「国際障害者分類(ICIDH)」の中で日常生活において支障・制約を受けている人と位置づけられている(3)。また日本の障害者手帳上の分類としては肢体不自由、知的障害、精神障害、視覚・聴覚・言語障害などがあり各重度や重複障害を含めると多岐にわたる。本論では社会生活上の問題や症状等によって障害者を分類せず、障害を持つことに起因した疎外状況そのものと芸術表現の関係に着目する。障害者を他者として疎外する状況を「障害者の他者性」と位置づける。 近年障害者芸術が注目を集め、障害を持つことをひとつの個性と考える気運が高まっている。しかし障害者という属性を強調し過ぎれば他者性が固定化される可能性がある。そうしないためには障害者に関わる芸術の認識、つくり手・受け手の意識を再構成する必要がある。障害者芸術をめぐる歴史的・文化的認識の再考によって、障害者の他者性は乗り越えられると仮定する。 一. 障害者芸術の位置づけに関する問題点 日本の障害者の表現が学問的に論じられる機会は少ない。まず作家が鑑賞を想定せずに制作したものを第三者が鑑賞の場に持ち出す場合があり、その際批評の射程が曖昧になるという問題がある。障害を持つ表現者より展覧会のディレクターや美術教育的サポーターの活躍に注目が集まることも多い。表現者が意図せずとも、他者が芸術的だと評価したものを芸術とみなすのかどうか。これは後に述べるアウトサイダー・アートの概念にも関係する観点である。 障害者芸術という枠でカテゴライズすること自体に問題がある。障害者が社会的不利益を受けていることは事実だが、彼らは人間として芸術に向き合っている。解決しなければならない社会的障害者問題と、表現に向かう人間存在としての障害者への理解は分けて考えなければならない。この二つの文脈が障害者芸術の論点を複雑にしている。社会的弱者としての障害者を批判してはならないという心理的抑制が働いた場合、作品の芸術性を問うことは妨げられてしまう。また障害者芸術とカテゴライズすれば、障害固有の表現があるかのような誤解を与える。 倫理観によって自然な感受性を抑止した鑑賞は義務的な儀式であり、本来の芸術鑑賞とは別のものになる。障害を持つ人々を善意の対象としてカテゴリー化すれば、彼らがどのような表現をしても礼賛するというう傾向を生み出す。このような礼賛は先住民問題にもある新たな社会疎外のひとつである。持ち上げ礼賛することで、障害を持つ人々が抱える現実的な生の困難は脱色される。鑑賞者はポジティブなイメージのみを享受して満足しがちであり、変わるべき社会的不利益や認識の問題は忘れ去られる可能性がある。善意の対象である障害者の芸術が単に素晴らしいという言説は、作品の個別性を無化するものである。 西洋において最初に注目が集まった障害者の表現は、アーティストにインスピレーションを与えるものであった。アカデミズムの枠外にいた彼らは自由を代行してくれる理想的存在として位置づけられた。この構造が日本における障害者芸術運動と結びつき、「社会に寄与する存在として障害者芸術をカテゴリー化する」という構図を作りだしたのではないか。その可能性を歴史的背景から検証する。 |
The theme of this paper is the otherness of disabled person in the art movement for disability, and the artistic expression. The art movement for disability in Japan against the background of the multicultualism has purposed raising image of disability as social welfare. But then the movement has the risk of driving to that disabled person is alienated from society with categorizing even admiration the artwork, before the matter about individual artistic expression. This is one of reason that the structure of Outsider Art in Europe was adapted without considering the difference in the historical backgrounds. On artistic criticism about the art of disabled person, there is tendency that refrains critical criticism by ethical bias. It’s for the traditional disability models that regard the disabled person as an object for goodwill or social unfortunate. But if the work is made to direct toward artistic communication, it isn’t the problem that the artist has disability or has not it. The disability is one of an opportunity that gives a mental necessity and strength for creation. The work is recognized as artistic expression, as not artistic therapy, that the creator expresses to assume conveyance, share and giving. The artificiality for the artistic sharing brings expression to art. It’s essential introspection in the case make public without intention of the said disabled person. And it’s the first step that everyone have realization what every person have possibility concern with disability, then revaluation as the artistic expression of disabled person, in order to carry to deconstruction of the otherness of disabled. It’s important reconsideration about the construction of social consciousness that need as relief of human image that conflict life between death. |
||||||||||
|
二. 西洋と日本における障害者芸術観 (一)アウトサイダー・アート 障害者の他者性と芸術の関係を基軸として、西洋と日本の状況を比較する。西洋における障害者の表現は、アウトサイダー・アートと呼ばれることが多い。この用語は美術史家ロジャー・カーディナルが1972年に確定したものである(4)。この場合のアウトサイダーという言葉は、「社会から隔離されている」ことではなく、「正式な美術教育のアウトサイドにいる」という点が重要であった。アウトサイダー・アートという言葉は「パラレル・ヴィジョン-二十世紀美術とアウトサイダー・アート」という展覧会を通じて、日本に広く知られることとなった(5)。これは一九九二年にロサンゼルス・カウンティ・ミュージアムで開催された展覧会で、翌年世田谷美術館に巡回している。日本における1990年代の障害者芸術運動にも影響を与えている(6)。しかし西洋におけるアウトサイダー・アートの概念は美術アカデミズムの存在が前提であり、日本はその伝統を共有していたとはいえない。この言葉のみが日本で使用されるとき「美術的伝統」というよりも「社会」の枠外に存在する障害者という印象を与えてしまう。その事実を当事者福利のために戦略的に使用した施設が後に述べる「工房しょうぶ」であり、アウトサイダー・アートの根本的構造を受け入れた活動が「エイブル・アート」である。 障害者の他者性はアウトサイダー・アートの中で構造的にどう位置づけられていたのだろうか。アウトサイダー・アートの概念とは1922年、ドイツ、ハイデンベルグ大学付属病院精神科医師だったハンス・プリンツホルン著作の『精神病者の芸術性(Bildnerei der Geisteskranken)』(7)という本から始まったものである。彼はヨーロッパ各地の精神病院から患者の精神状態を解釈するための作品を五千点以上も集め、これらに芸術的価値を見いだそうとした (8)。第一次世界大戦後、機械技術崇拝の近代文明に疑問を呈した芸術家たちは、文明社会の枠組み外にあった視覚表現にひきつけられた。一九二四年に「シュルレアリズム宣言」を行ったアンドレ・ブルドン(1893〜1966)はこの本に掲載されていたアドルフ・ヴェルフリ(図1)などの作品を調査した結果、精神病患者たちが強制されずに制作された芸術を「健全な良心の宝庫だ」と絶賛するにいたった。フロッタージュなど合理的表現を裏切る方法を求めたマックス・エルンスト(1891〜1976)は1922年にドイツからパリへ『精神病者の芸術性』を携えて入国しパリの作家に影響を与えた。この本からの引用と思われる作品も制作している。(図2)(図3) 『精神病者の芸術性』を巡る状況は狂気への興味を喚起し、精神障害者の表現に対する再評価をもたらした。しかし障害者の疎外状況を改善するという意識はみられない。シュルレアリストたちは自らと精神障害者とは違うという姿勢をとった。サルバドール・ダリ(1904〜1989)は「私と狂人との違いは、私が狂人ではないことである。」と主張している。しかし実際に精神疾病を抱えながらシュルレアリストとして活動した作家がいる。アントナン・アルトー(1896〜1948)である。彼は一九二六年までシュルレアリスト研究所で活動し、文筆活動や演劇において人間の残虐性を描写した。一九三七年から精神病院に監禁され電気ショック療法による治療を受ける。人間の顔は死の領土だと語り、絞首刑や凶器が突き刺さった頭部を病院内で描き続けた。ロジャー・カーディナルはアルトーの自画像(図4)について「シュルレアリストたちの枠組みの限界をさらすように、何ものの真似でもない本物の刻印を示している。」と評した (9)。精神病院内で制作されたアルトーの作品は、パラレル・ビジョン展においてアウトサイダー・アートとして紹介されている。美術アカデミズムの外部にいることがアウトサイダーの条件ならば、アルトーは除外されるべきである。よってアウトサイダー・アートの位置づけには「(健常者の)社会から逸脱、または引き離された状況で生み出された」というニュアンスが含まれていると筆者は考える。
(二)アール・ブリュット 第二次世界大戦中、ナチスは精神病患者を遺伝的劣等人種として抹殺していく。一九三七年にナチス美学にそぐわないとしてモダンアートを誹謗排斥する「頽廃芸術」展が開かれる。モダン・アーティストらを卑しめるための比較材料としてプリンツホルン・コレクションが利用された。大戦中は誹謗対象であった精神病患者の作品に、再度光をあてたのはジャン・デュビュッフェ(1901〜1985)であった。当時彼は画壇のエリート主義を憎み、また独自の作風作りに悩んでいた。彼は『精神病者の芸術性』を入手した際、伝統の枠をはずれたところに表現の可能性があることを発見し、驚喜した。一九四五年にスイスにおいて精神病患者の作品収集を行う。(図5)デュビュッフェは伝統や評価の支配から解放されたこれらの芸術を「アール・ブリュット(調理されていない、生の芸術)」と名付けた。一九七六年スイスのローザンヌにアール・ブリュット美術館がオープンする(10)。ここでは美術的教育を受けずに自由に創作したこと自体が重視され、その境界における社会的差別意識は希薄である。 西洋におけるアウトサイダー・アートやアール・ブリュットは先駆的・独創的な創造を強要する近代アートシーンの重圧が必要とした「発想の源泉」である。アウトサイダー・アーティスト自身が作品発表への意志を持っていたか否かなど、彼らの主体性は問題視されていない。彼らは単に見いだされる存在である。アウトサイダー・アートとアール・ブリュットの構造によって、アウトサイダー側が益するものは殆どない。社会から距離があることが独自な表現を生み出す要因なのである。つまり疎外状況を肯定的に考える構造なのである。これらの概念を日本に取り入れる場合、歴史的背景の違いに意識的になる必要がある。意識的でなければ差別的境界をなくすためにアウトサイダー・アート的な構造を取り入れるということに矛盾が生じる。
(三)日本における障害と芸術文化 疎外状況を比較的肯定的に考えるアウトサイダー・アートの構造が、日本において発生しなかった文化的要因とは何か。また障害をめぐる芸術文化は日本においてどのような歴史的な位置づけだったのだろうか。 日本における古い民間伝承に福子伝説というものがある。障害児が生まれるとその家は栄えるというものである。この福子伝説は障害児を生かすことに役立ったと言われる。平安時代は芸能集団傀儡にカリエス、くる病、視覚障害者などが加わることもあった(11)。鎌倉時代には平家物語を語り継ぐ視覚障害者の琵琶法師が存在した。江戸時代の検校制度によって、琴の教育に携わる視覚障害者たちもいた(12)。障害者が社会生活を営む上でその芸術・芸能を経済的自立のための手段にする、という意識が歴史的に存在していたのである。 福子伝説による相互扶助や隣保制度の連帯責任などが障害者にプラスに働いた一方で、日本独特の差別意識である業病説も存在していた。平安時代、法華経を書写していた女性をそしった罰として「白癩(ハンセン病)」になるという話があり、これが後に業病説となる(13)。過去世の罪業の因果応報として病を発生する、つまり「病は罪の結果」という考え方である。これはハンセン病などの感染病への恐怖と深刻な差別意識を生み出した。また、明治以降、富国強兵制度のもと、産業化と効率性が重視されるようになり、障害者は能力を持たないものとして社会から隔絶されることになった。業病説と近世の帝国主義は、障害者を心理的も社会的にも隔離する方向を生み出したのである。 一九三六年、ハンセン病患者である作家・北条民雄が隔離の現実を「いのちの初夜」によって世に問いかけた(14)。1904年(明治40年)「らい予防に関する件」という法律(15)で終生隔離がうたわれ、ハンセン病者は警察によって強制的に療養所に収容された。「強制隔離」という姿勢は、ハンセン病は恐ろしいものであるという意識を形成していった。療養所では断種と堕胎が行われ、患者の生は徹底的に否定されていったのである(16)。 このような優性思想は日本に根強く残った。優生保護法の中で1996年まで様々な障害児の堕胎を認めてきたという歴史が日本にはある。このような背景のもと、障害を恐怖のまなざしや差別の対象とする意識に対して、社会運動的な要素が強くあらわれることになる。 ハンス.プリンツホルンのように、精神的疾患をもつ表現者に注目した精神科医師が日本にもいた。式場龍三郎(1898〜1965)である。東京深川に建てられた怪建築「二笑亭」(17)や、知的障害者の山下清を世に紹介した。しかし、これらは日本のアーティストに対してプリンツホルン・コレクションのように大きな影響を与えなかった。独自の作風作りに重圧を感じるほどの西洋の美術的伝統を、日本の芸術シーンが共有していなかったからである。評価軸が確立していない分野は黙視された(18)。 1960年代から社会周辺部に属するとされてきた女性、少数民族などの社会運動が台頭し、障害者解放運動もその連鎖のうちにあった。脳性麻痺者社会福祉団体の「青い芝の会(1957年発足)」の行動綱領のなかで「脳性麻痺者固有の文化を創り出す」という文言がある。その後の障害者自立生活運動に青い芝の会が与えた影響は大きい。健常者文化への対抗そのものが目的化する危険性もはらんでいたが、バス闘争など身体を使った過激な抗議は、一種の社会的パフォーマンスであった(19)。 その後社会運動も形を変えていき、障害者が書籍や講演などを通して主体的に社会に発信する機会が増えていった。安積遊歩(一九五六年〜)は「車イスからの宣戦布告」等の著作と自らの出産によって障害者の生と性への抑圧を訴え、優生保護法改訂の糸口を作った(20)。安積は「障害をもつ人々は社会に想像力を与える存在である」という気づきから自己肯定感を得たという。変わるべきなのは、社会的側面や人々の無知であるという事を主張している(21)。表現を通して、当事者の世界観が社会側の想像力にアプローチするという可能性を安積は示している。 しかしながら、この時期にいたっても日本の芸術分野では障害者の作品を古典的障害者観抜きに評価することは難しい状況だった。古典的障害者観とは、障害者は医療観点での障害であり、善意の対象であるという視点である(22)。障害者の芸術活動は経済的自立の手段という認識のもと、鑑賞者が慈善として作品を購入する場合が多かった(23)。障害を持つ作家の作品は、福祉的視野を通して認知される傾向が強い。障害を持ちながら口でくわえた筆で詩画を描く星野富弘(1946年〜)の作品を集めた富弘美術館は、1991年のリニューアル九六日目で入館者十万人を越えた。現在も年間40万人が訪れる人気の美術館である(24)。しかしその作品群は、批判や競争原理が働く美術界の評価軸で語られることはほとんどない。 古典的障害者観を、作品性という観点でアーティスト側が乗り越えている場合もある。沖縄に「土の宿」を経営している木村浩子(1937年〜)がいる。彼女は脳性麻痺障害を持つ画家である。絵本作家の田島征彦(1940年〜)は木村の生き様に心酔しているが、彼女が描く典型的子供像に関しては「命のない人形ではないか」と本人に進言している。翌日木村は小学校で子どもたちを観察し「今まで子どもの魅力を見逃していた」と高揚して田島に語る(25)。古典的障害者観を払拭する作家としての彼らの交流は、自他の作品性を基盤として成されたものである。 古典的障害者観は倫理的バイヤスとなり「弱者として設定された障害者」の作品について語ることをためらわせる。当事者にとって売ることが最優先されるなどの状況を加味しつつも、本来はその作品の出来・不出来について感じてよいはずである。作家が発表することを想定する、つまり批評空間にさらすことを意識した作品ならば鑑賞者は倫理的バイヤスを離れて観るべきである。しかし当事者ではないディレクターのモチベーションで発表する場合がある。そこではディレクターの目的に合致しているかどうか、ディレクションの質はどうかという点が重視される。さらに芸術的感動だけではなく福祉的な目的があった場合、作品批評の射程は複雑さを増す。
|
|
||||||||||
|
三. 障害者芸術運動の具合的事例 九十年代に障害者の表現に注目が集まったひとつの要因として、多文化主義(multiculturalism) (26)を背景に他者へのまなざしが意識化されたことがあげられる。前述した「パラレル・ヴィジョン」展に始まり、障害者にかかわる展覧会が企画されることが増えていった。展覧会の呼称として「アウトサイダー・アート巡回展」「エイブル・アート'99東京展 ーこのアートで元気になる」「スーパーピュア」「ナイーブな絵画展」など、ほとんど障害者という言葉を用いずにカタカナ表記が使われている (27)。 障害者へのイメージをポジティブなものに代替しようという意識がみてとれる。この中で障害者のイメージを高めるという社会目的を強く押し出した活動がエイブル・アートであった。 1993年、「障害者芸術文化ネットワーク準備委員会」(後のエイブル・アート・ジャパン)が障害者芸術文化活動に関する実態調査を行う (28)。これは全国の福祉施設や作業所を結びつけることが目的だった。この研究結果がエイブル・アート・ムーブメントの基盤となる。エイブル・アートとは、一九九五年、播磨康夫(NPOたんぽぽの家理事長)が提唱した概念である。「人間に希望を与える新しい芸術」として障害者芸術の再評価を求めた。「このアートで元気になる」というエイブル・アート展覧会の副題にもその意図が表れている(29)。この活動が社会に寄与した側面として関係施設の情報交換が頻繁になったこと、創造活動の環境やスキルの改善が進んだこと等があげられる。また各地の創造活動をひとつにまとめることで、行政・企業からの援助を受けやすくなっている(30)。エイブル・アート・ムーブメントはアドボカシーのための社会運動である。展覧会だけでなく頻繁にシンポジウムを開き、各施設や障害者共同作業所関係者の多くをパネラーとして迎えている。そのためそれらすべてがエイブル・アートという意識を共有している印象を与え、活動範囲を限定することが難しい。播磨はエイブル・アートの定義を「障害のある人たちのアートを〈可能性の芸術〉としてとらえ、生命力を失いつつある現代社会に生きる人たちが、アートを通して人間性を恢復(かいふく)させ、さらに芸術と社会の新しいコミュニティーを築いていく〈市民芸術運動〉」とした (31)。このコンセプトをみるかぎり「障害者芸術は現代人の現状を打破するもの」という印象を受ける。この構造は西洋のアウトサイダー・アートに近い。アウトサイダー・アートは苦悩するモダン・アーティストが見出した救済であった。エイブル・アートの場合、救済をもとめているのはモダン・アーティストでなく、閉塞的社会状況に苦しむ現代人ということになる。 障害者の表現には、不自由な身体による独特のタッチ、あるものへの圧倒的執着など、その表現者でしかあらわせない独創性がある場合が多い。人々は作品の美的価値を論議する以前に、人間の魂や身体がもともともっている個別性に出会った感動を享受する。またエイブル・アートは、世界を感じ表現する当事者のまなざしと主体を意識化させる。しかし、障害者をカテゴリー化し、持ち上げによる社会疎外を再生産していく危険性もあわせもっている。エイブル・アートとされた作品の魅力は閉じられた自己の苦悩にある場合も多い。だからこそ鑑賞によって当事者の精神的リアリティに寄り添う可能性がある。それを一概に「現代人を元気づける表現」と言い切ってしまうことには抵抗を感じる鑑賞者も多いであろう。エイブル・アートは新しい芸術というよりも、個別な障害者の生に対する社会側の想像力を豊かにする準備段階を担ったと筆者は位置付ける。社会的包容力を拡大しながら差別意識を乗り越えようとする施設として、他に「ボーダレス・アートミュージアムNO-MA」(2004年開館)がある。ここは障害障害のみならずあらゆる境界を越える表現を指向している。エイブル・アートの中心である「NPOたんぽぽの家」のように障害者の生活上のサポートとは直結していない。純粋にミュージアムとして独立している。 障害者と健常者のスタンスの違いに、意識的になることから出発しようとしている施設が知的障害者施設しょうぶ学園「工房しょうぶ」である。この施設の巡回展名には、アウトサイダーという言葉をあえて使っている。代表・福森伸は「健常者とのスタンスの違いをみつめ、そこから始めていくという感覚の重要性」を呈した(32)。この施設は、特に刺繍の分野で斬新な作品を生み出している。(図6)色面が立体として浮き上がるほどに差し込まれる針と糸。その行為とこだわりの集積と集中力が、みるものを圧倒する。これを福森は「〈縫う〉という行為そのものが素材のもつ可能な限りの〈強いできごと〉を出現させている。それは作者が〈創り出す作品〉よりも〈創り出すための時間と行為〉に幸福を感じているからである。」と表現している (33)。また彼は作家の経済的福利も視野に入れている。障害者の芸術表現が経済的自立の手段であるという認識は日本が近世から培ってきた側面でもあるが、その際福森は「障害」を誇張し周囲の想像によって作家像を作り上げないよう留意するという。作家や家族の望む生き方をまず尊重し、芸術活動を通して共に考える援助の姿勢を福祉のひとつとして考えている。作家が主体であり、周囲は芸術活動を通して共に考える援助者なのだという (34)。この場合、無為の行為を芸術とみなし発表する援助者(ディレクションに関わる周囲)は批評にさらされるという自覚が必要となる。援助者は当事者との福祉の関係と、鑑賞者との間に生まれる批評空間に責任を負うことになる。 工房しょうぶの他に障害者と健常者のスタンスの違いを意識化させる表現として「ドッグレッグス」があげられる。1991年に旗揚げされた障害者のプロレス集団である。代表の北島行徳が書いた「無敵のハンディキャップ」は講談社ノンフィクション賞を受賞している。彼は障害を持つメンバーにこう語る。「健常者の方からすれば、同じ人間という言葉は免罪符みたいなもんなんだよ。同じということで、障害者について考えることをやめているのが現状なんだよ。…それが結果的に無関心を呼んで、回り回ってお前の苦しみに返ってくるんだよ。」(35)障害者と健常者の違いを認め合い相互に受けとめなければ、効率優先の世の中に障害者が溶けこむことが難しい、と彼は語る。美的要素に特化した表現ではないが、障害を持つ肉体を全面に押しだしたパフォーマンスは「人間はぶつかりあうことを放棄してはならない」というメッセージを放っている。 解決すべき障害者の社会的困難を無化して、障害者と健常者の境界をなくしてしまうのは問題である。しかし障害者という属性を、全ての表現に関係づける必要性については熟考を要する。芸術的側面と社会的側面の双方から慎重に意識を深めなくてはならない。
|
|
||||||||||
|
四.障害者の他者性と表現の可能性 (一)障害者の他者性 障害者の他者性を乗り越えるためには、障害者の生に肯定的なイメージを付加する方向と、「社会的不利益を感じている側からみた壁」を意識化させる必要があるという二つのベクトルが90年代の障害者芸術文化を交差していた。 障害者と健常者という二者対立の社会的認識に対して、新しい視点をなげかけた現代美術家がいる。「すべての人は障碍者である」(36)と提唱した和田千秋(1957〜)である。彼は障碍児の親として障碍を受容する過程を作品化した作家である(図7)。いつ病気や事故で障碍を追うかもしれないという意味で人はすべて潜在的な障碍者である、と彼はいう。高齢化社会という観点からも障碍を引き受けケアする立場になるという可能性は高い。和田は芸術表現を通じて障碍に対する(主に健常者側の)意識を揺さぶっている。障害者の他者性を脱構築する鍵が、彼の認識に内在している。障碍の問題を自らのものとして思考する姿勢によって、自己を共同体の可能的一員とする意識が開く。しかし当事者である障碍者自身の表現のクオリティーについてどう捉えるかという問題は依然として残る。
(二)表現の可能性 表現とは目に見えないもの(作家の精神的個性など)を外化することである。インターネット環境が充実した現代社会では、権威に頼らずとも「個」としての表現を発信しやすくなった。美術における表現様式も多様化しており、誰もが独自の方法で表現者になる可能性がある。それらの表現が芸術的であるという直感的判断は、学識に依拠せず各自が主体的に持つ時代になるだろう。では表現を「芸術」だと判断するその契機とは何か。 美学者・佐々木健一(1943年〜)は芸術がいくつかの契機によって構成された複合体であるとした。技術(改造する力)・知(認識)・作品(美)・冒険的精神(快)という四つの契機に根ざすとし、常に現状を超えてゆこうとする精神の冒険性は他の契機を現実化し一体化する力として働くという。これらの契機に根ざし、美的コミュニケーションを指向する活動を芸術と定義づけた (37)。これは美を媒介とし自己を他に対して共感させうる能力を根拠としている。 美的コミュニケーション、現状を超えようとする意志というキーワードをもとに、筆者が関わった障害者芸術活動を紹介する。2000年に「日常点」という写真展を行った 。障害の有無に関わらずレンズ付きフィルム(インスタントカメラ)を渡し、自分からみた日常を撮影してもらう。参加者の中には視覚障害者もいた。撮影された写真を全て各箱におさめ、鑑賞者は箱の中の写真を手にとって鑑賞するというものだった。作家名表記は任意である。「障害者は見出される被写体ではなく主体として世界を見るものであり、作品は鑑賞者がその主体に寄り添う契機である。」というコンセプトが中心にあった。まなざしや境界という概念へのアプローチに重きをおいたため、感動を与えうる作品としてのクオリティーを問題にできなかった(38)。 表現者側の意志力と共感への可能性について示唆を与えたのは、同実行委員会主催のフォーラムにスピーカーとして招いた山口進一(1938〜2006)だった。ALS(筋委縮側索硬化症)患者である山口はコンピュータを駆使して患者同士のネットワークを構築し、他者との繋がりは精神的生命を支えていると語った。また「私は表現しなければ生きていけない」と断言し、最後まで自分の肉声でコミュニケーションし続けるために音のデータベース研究に参加していた。フォーラムの中で音声合成システムによる声で彼は「あいだにあるもの」という詩の朗読を行った(39)。そこには声の一音が独自の表現となりえる可能性と、表現に対して個としての存在をかけているという意識の重さがあった。美的要素は不十分であったにしても、表現者側が自己探求の意志や関係性への認識を明解に持っていることが前述の写真展とは違う点であった。 展示空間全体で美的コミュニケーションへの可能性を示した作家が河合正嗣(1978〜)である。作品をモデルと関わりの深い場所にサイトスペシフィックに展示することで、「生死」という普遍的テーマに向かいあった。彼はデュシェンヌ型筋ジストロフィーを患いながら、入院患者や病院スタッフのデッサン「110人の微笑む肖像画」を描き続けている。(図8)これらの作品は彼が気管切開手術をした足助病院に展示された(40)。これは病める人々を救うため、または社会的包容力を拡大するためという視点でのアート活動ではない。彼が表現したかったものは病院という場に存在する繋がりの自覚、自らの痛みを開き他者に寄り添う、そのリアリティである。会期中鑑賞者は、少人数のチームに別れ病院内を鑑賞する。鑑賞者は自らが病院関係者ではないことを意識しながら、病や生死に近い場にいるという病院の空気感そのものを作品として体験していく。彼の場合「障害を持つこと」が問題の中心ではなく、その困難によって熟成された眼差しを他者と分かち合うことが重要なのである。入院患者は各自のナイーブな事情や弱さをさらけだしながら生活空間を共有している。河合はそれを絵そのものというより絵のあいだにあるもので表現しようとしている。入院病棟内の関係性から(病院外部の)薄れゆく繋がりを指摘する、と彼は云う(41)。その展示空間は、彼の生を支えた「関わり」にとって必然的な場である。連作による様式や展示・鑑賞方法にいたるまで作家の明快なコンセプトによって貫かれており、全体で人間の生死を題材としたひとつの表現に結実していた。 障害者の他者性を表現の力で乗り越えているアーティストもいる。劇団「態変」(1983〜)である。障害自体を表現力に転じ未踏の美を創出しようとするパフォーマンス集団である。中心人物である金満里のコンセプトや表現力には卓越したものがある。障害を持つ身体そのものが表現の独自性となり、観るものを圧倒する強さを放つ。彼らは自らの活動が障害者の社会運動と混同して語られることに抵抗し続けてきた(42)。態変は人間の普遍的テーマとして身体を注視し、観客との間に純粋な美的コミュニケーションを求めている。 以上の事例から、作家が意図的に表出する美的表現と主体的に美的体験を咀嚼する鑑賞者が、作品を通じて出会う領域を筆者は芸術と位置づける。双方の主体性によってうみだされた新しい精神的領域である。「芸術の始源に関して子供や精神病患者のように教育を受けていない状態ほど叡智の源泉だ。」とパウル・クレー(1879〜1940)は言及した(43)。確かに無作為の表現が感動を与えることはある。しかし精神的個性の表出である芸術療法的所産と芸術表現は違うと筆者は考える。芸術の始源を芸術に至らしめるのは、美的共有への「作為」である。主体的に美的共有を希求する活動を芸術と位置づけた場合、障害者・健常者という属性を問題にする必要はなくなる。作家の主体的意志の有無によるからである。その領域ではじめて障害者の他者性は乗り越えられる。しかし道義的に障害者の社会的不利益に無関心のまま他者性は乗り越えてはならない。属性を安易に切り捨てれば、障害者の生活上の困難まで意識化されなくなる。障害者の芸術表現に向き合う場合、社会的側面と芸術性の両方に目配りする慎重さが必要なのである。 |
|
||||||||||
|
おわりに 善意の対象、あるいは救いとして「障害者」をとらえる社会意識とは何か。社会規範や価値観の解体によって「自らの〈生〉が押し込まれている」という閉塞感が若い世代を中心に浸透している(44)。その裏返しで「生死をみつめて必死に生きる人間」像を彼らは救いとして必要とするのだ。変わるべきなのは閉塞的社会意識である。「周辺」を必要とする意識構造自体を脱構築しなくてはならない。苦痛を障害の他者性に代行してもらいさらに救済してもらおうという不遜が、当事者たちの現状を歪めて把握させる。押し付けているイメージが当事者の自由を奪っていることに気がつかない。オーディエンスが傍観者として無自覚に障害者を他者化していることが問題の核心なのである。生死やリスクに向き合う生き様を、他者に代行させずに自らの問題として思考できるかどうか。「生死をみつめて必死に生きる〈周辺〉」を必要とする人間側が逃避しているもの、障害をめぐる芸術文化はそれを静かに示している。 たとえ重度の障害があったとしても人間は主体として世界を感じそれを表現している。障害を持たない人間が、その当事者に寄り添い実感するという意味ですべての表現は認められなくてはならない。表現者の内面世界に寄り添い認め合う契機としての可能性を否定はしない。ただし、そこで問われる表現の質は作家の存在と等価になるほど打ち込まれたものかどうか、他者に与える影響力があるかに現れる。確かに障害者の表現から、拭えない個が存在の中に既にあるという事実が伝わることは多い。しかしそれだけでなく作品完成に至る苦闘を引き受けつつ、美的コミュニケーションによって他者に与えるものを見いだした人間を筆者は芸術家と呼びたい。その領域では障害が表現に精神的必然性と強度を与える契機のひとつとなる。芸術療法の所産ではなく芸術的表現として自他が認識する作品とは、伝えること、分かち合うこと、与えることを作家が想定しているものである。福祉的目的以外で周囲の人間が作品公開を強く望む場合は、一層慎重さが求められる。表現者は本心に向き合い自分の弱さをさらけ出し、賛否両論を受ける勇気が問われる。感じているものに真実味があるか、その切実さや葛藤の度合いが表現の質を決める。内的なものが具体化し結実した表現に自己存在と等価になるものが込められるとき、そこに命が宿り他者の真実を突き動かす。 全ての人間は障害をもつ可能性を抱えている。しかし障害を持つことを自らの可能性として思考しないことが、障害者を他者として疎外する状況を生み出している。障害者を他者として疎外する状況を乗り越えるには、鑑賞者が障害を持つことを自らの問題として引き受けることが必要である。そして作品性を観ずに、障害者芸術をカテゴライズして礼賛する姿勢を正さなければならない。また障害を持つ表現者も美的共有を指向することが大切である。障害を持つ表現者と鑑賞者が、主体的に歩み寄る精神的領域こそが芸術であり、そこに社会的疎外は存在しない。つまり障害者芸術の他者性を乗り越えるには、二つの方向から共に歩み寄っていくことが必要なのである。まずオーディエンスが障害を自らの可能性と想定し、他者性を必要とする構造を脱構築すること。そして表現者が美的コミュニケーションを指向し、障害の有無を越えた芸術表現に挑み続けること。この両輪は互いを必要としながら、生の困難の意味を変えていくだろう。 |
|||||||||||
|
註 (1)障害者という表記に関して、近年「害」という字が与える印象を考慮して「障がい者」「障碍者」「障害を持つ人々」と表す傾向にある。 (2)断種は優生学によって世界的に行われた。日本では1948年に優生保護法が成立し「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する(第一条)」と記された。1994年、カイロ国際人口会議で安積遊歩が優生保護法と子宮摘出の問題をアピールする。(1996年に改訂され母体保護法と名称を変更) (3) 2001年の世界保健機構(WHO)「国際障害者分類(ICIDH)」においては機能・構造 (body function and structure)、活動 (activity)、参加 (participation)における支障・制約して障害を分類している。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課「国際生活機能分類国際障害分類改訂版」 (4)この用語は美術史家ロジャー・カーディナルが1972年に確定したものである。Roger Cardinal, Outsider Art (New York:Praeger,1972) (5)一九九二年にロサンゼルス・カウンティ・ミュージアムで開催され、翌年世田谷美術館に巡回している。主流(インサイダー)とアウトサイダーは単にスタイル上での相似だけでなく、創作の姿勢自体を同じくするパラレルな関係にあると位置づけられた。 モーリス・タックスマン、キャロス・Sエリエル編『パラレル・ヴィジョン-二十世紀美術とアウトサイダー・アート』(淡交社 1993年) (6)資生堂ザ・ギンザアートスペースでは1991年から10年間、アール・ブリュット美術館所蔵品 がアウトサイダー・アートとして紹介されている。障害者の芸術をあつかった展覧会の呼称にも使用された。「工房しょうぶ アウトサイダー・アート巡回展」 サボアヴィーブル他 1999年〜2000年がある。 (7) Hans Prinzhorn, Bildnerei der Geisteskranken (Berlin: Springer, 1922) (8)服部正『アウトサイダー・アート』(光文社新書 2003年) 60頁 (9)ロジャー・カーディナル「シュルレアリスムとその創造的主体の枠組み」前掲書『パラレルビジョン』112頁 (10)『芸術新潮』第四巻十二号 (新潮社 1993年) 68頁 (11)カリエスは結核後遺症による障害、くる病は乳幼児期に起きる骨格異常である。 (12)花田春兆「日本の障害者の歴史」財団法人 日本障害者リハビリテーション協会発行『リハビリテーション研究』第五四号(1987年)2〜8頁 (13)「若し復是の経典(法華経)を受持せん者を見て、其の過悪を出さんか、若しは実にもあれ、若しは不実にもあれ、此の人は現世に白癩の病を得ん」妙法蓮華経普賢菩薩勧発品第二十八 (14)川端康成・川端香男里・編『定本 北条民雄全集 上』(東京創元社 1996年) (15)高松宮記念ハンセン病資料館『高松宮記念ハンセン病資料館十周年記念誌』(社会法人ふれあい福祉協会 2004年)178頁 (16)国立ハンセン病資料館『国立ハンセン病資料館 開館記念誌』(社会法人ふれあい福祉協会 2004年)16〜22頁 (17)式場隆三郎、藤森照信、赤瀬川原平、岸武臣、式場隆成「定本二笑亭綺譚」(筑摩書房 1993年) (18)「式場の黙殺を決め込んだ美術の専門家達にとって、同様に山下清を黙殺することはたやすかった。それは美術の問題ではなく、教育の問題でしかなかった。」服部、前掲書 103〜104頁 (19) バス闘争」とは、障害者の乗車を拒否したバスの前に青い芝の会のメンバーが寝転がり、乗車をさせるべきだと訴えた運動である。「自立生活運動」とは、障害を持つ当事者自身が自己決定権や自己選択権を育てあい、支えあって、隔離されることなく、平等に社会参加していくことを目指すものである。樋口恵子「日本の自立生活運動史」全国自立生活センター協議会『自立生活運動と障害文化-当事者からの福祉論』(現代書館 2001年)18〜19頁 (20) 障害者の性やジェンダーの問題に言及した安積遊歩の著作として『癒しのセクシートリップ』(太郎次郎社 1993年)、『女に選ばれる男たち』(太郎次郎社2001年)、「共生する身体:セクシュアリティを肯定すること」『越境する知(1)』(東京大学出版会 2000年)がある (21)知足美加子主催「安積遊歩講演会」講演録 2007年7月12日於・NPO法人エスタスカーサ http://www.design.kyushu-u.ac.jp/~tomotari/asakadeta.html(2007.11.16取得) (22)米国の障害者研究者クロッグストン、ベス・ハラーの研究による用語 岩隈美穂「異文化コミュニケーション、マスコミュニケーション、そして障がい者」青土社『現代思想 特集・身体障害者』 Vol.26-2 (1998年)199頁 (23)並木誠士、中川理『美術館の可能性』(学芸出版社 2006年) 161頁 (24) 現在でも特別支援学校や障害者共同作業所など福祉関係団体で行われるバザーは、慈善的な目的で行われる場合が多い。 (25)木村浩子『おきなわ土の宿物語』(小学館1995年)103頁 (26)ひとつの国家ないし社会の内部に、複数の異なる文化が共存できる集団間の政治的・経済的・社会的な不平等を是正しようとする運動および主張。八十年代後半からアメリカでは白人・男性文化偏重を正そうとする多文化教育運動が起こり、これがマイノリティへの差別表現を摘発する「ポリティカル・コレクトネス(PC)」運動を派生させている。『岩波哲学・思想事典』(岩波書店 1998年)1031頁 (27)「工房しょうぶ アウトサイダー・アート巡回展」 (サボアヴィーブル他 1999年〜2000年 、「エイブルアート'99東京展」東京都美術館1999年)、「スーパーピュア2001,2005」(横浜トリエンナーレ 2001年,2005年)、「ナイーブな絵画展」(福岡市美術館 2002年) (28)『障害者文化芸術振興に関する実証的研究事業報告書 平成6年度』(財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 1995年) (29)播磨康夫『アートフル・アドボガシー 生命の、美の、優しさの恢復 芸術とヘルスケアのハンドブック』(財団法人たんぽぽの家 1999年)1頁 (30)エイブル・アートは一九九六年からトヨタ自動車株式会社や富士ゼロック株式会社などの企業からの支援を受けている。「エイブル・アート・アワード」として、障害者が関わる創作活動の制作支援と展覧会支援をエイブル・アート・ジャパン(旧障害者芸術協会)側も行っている。エイブル・アート・ジャパンオフィシャルサイトhttp://www.ableart.org/(2007.11.15取得) (31) 前掲HP (32)知的障害者施設しょうぶ学園工房しょうぶ 『季刊しょうぶ』冬号(2000年) (33)福森伸「制作の現場から」工房しょうぶ『縫 nui project2-』 (DoArt2007年)3頁 (34)福森伸 筆者宛メール書簡 2007年1月11日 (35)北島行徳『無敵のハンディキャップ』(文春文庫1999年)108頁 (36)「障害」はドイツの医学用語からの翻訳語はもともと「障碍」であった。否定的な意味合いをもとに戻すため和田は意図的に「障碍」という文字を作品に用いている。『障碍の美術・現代美術のリハビリテーション和田千秋展』(朝日新聞社1996年)4頁 (37)佐々木健一『美学辞典』(東京大学出版会 1995年)31頁〜35頁 (38)筆者はエイブル・アート福岡実行委員長として「芸術とヘルスケアフォーラム」の福岡開催と写真展「日常点」(ギャラリー笑門 2000年11月24日〜26日)を、福祉作業所「工房まる」のメンバーを中心に行った。写真展示会は作品のクオリティーについては問わなかった。そのため作品が各日常生活への興味を喚起する媒体にとどまる危険性があった。また批評の射程は作品性ではなくディレクションに向けられることになり、各表現をディレクションの素材として扱うことへの良心的課題を残した。 (39)エイブル・アート福岡主催「講演録 芸術とヘルスケア・パネルディスカッション」(於・福岡アジア美術館あじびホール 2000年10月7日) http://www.disign.kyushu-u.ac.jp/~tomotari/yamaguchi2.html(2007.11.16取得) (40)「河合正嗣絵画展YOU LIVE NOW」2007年8月13日〜9月11日)於・愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 院長・早川富博は文化的地域作りに貢献する病院をめざしており、名古屋造形大学准教授・高橋伸行と共に「やさしい美術プロジェクト」も行っている。 (41)河合正嗣 筆者宛メール書簡 2006年10月25日 (42)態変事務局 筆者宛メール書簡 2007年3月8日 (43) Paul Klee, Der Blaue Reiter (Die Alpen 6-5,1912) (44)樫尾直樹「死を確かに後ろに感じながら生きる−現代若者の死生観と情念」樫尾直樹・編『スピリチュアリティを生きる』(せりか書房 2002年)74頁 |