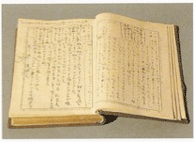|
はじめに アウトサイダー・アートとアール・ブリュット 日本における障害者芸術運動 /エイブル・アート/工房まる/和田千秋/工房しょうぶ/アトリエブラヴォ/アリヤ おわりに
|
|||||||||
|
はじめに 『精神』というドキュメント映画の中で、長年統合失調症を抱えてきた患者はこう語る。 「ほんで、自分は確かに病気をもっとる。ほんなら健常者は完璧かというたら、おらんのですよ、そんな人は。僕の目から見たら人間はね、精神障害であれ普通の人であれね、いわゆる全人的に〈健〉状態の人は、この世の中探しても一人もいないんすよ。一人もいないんすよ!」[1] 監督の想田和弘は精神科診療所「コラール岡山」の患者達を被写体とし、モザイクなしでスクリーンに映し出した。想田自身も燃え尽き症候群と診断された経験をもつ。その際「病気の世界」と「健康な世界」は地続きであること。また、障害に関する社会の偏見の強さを痛感したという。障害(精神および身体)の問題は、往々にして人々の意識や想像力・社会的包容力の中にある。想田と同様、私たちは「健常」と「障害」の間に横たわるグラデーションの中にいるのである。自らが傍観者ではなく潜在的な当事者(その家族)であると思考するとき、無意識に切り離してきた世界が立ち上がってくる。人々の想像力を掻き広げる媒体のひとつが芸術表現である。表現は作家の存在の叫びである。鑑賞者は作家の主体を認知し、その世界観に感情移入できる。障害をもつ当事者の表現とその社会的受容を見つめることで、グラデーションが自分の足もとから伸びる様を明らかにできるかもしれない。 障害者の芸術表現について、欧米では美術アカデミズムを前提にした独自性に注目が集まる傾向があり、日本では社会的差別問題解決の糸口として語られる場合が多い。欧米に端を発した障害者芸術のカテゴライズは、九十年代の日本において障害者社会運動の手段として利用されていく。この歴史的経緯や福祉観の存在が、障害者の芸術を語ることを複雑にしている。障害者芸術を語るとき、その属性と芸術性、福祉的側面のバランスをとることが難しい。「障害者という属性によって、その作品に芸術的な価値が付加されるのか」という問題がつきまとう。 日本において「障害者の」という属性が押し出されている場合は、福祉的側面に軸足がある。しかし鑑賞者側の問題として、障害者芸術の安易なカテゴライズは、個別な芸術性を問う前に礼賛する傾向を生む。そこでは思惑に反して、障害者の社会的不利益は忘却されがちだ。また芸術活動そのものが「障害は個性」という考え方を強化する傾向にあるが、この心理的側面は障害者の生活上の困難とは別問題なのである。前述したグラデーションの自覚とは、この社会的不利益を自らの問題として思索するための心理的装置であり、決して透明化するためのものではない。障害者のプロレス集団「ドッグレッグス」を率いる北島行徳は障害を持つメンバーにこう語る。「健常者の方からすれば、同じ人間という言葉は免罪符みたいなもんなんだよ。同じということで、障害者について考えることをやめているのが現状なんだよ。…それが結果的に無関心を呼んで、回り回ってお前の苦しみに返ってくるんだよ。」[2]障害者と健常者の違いを認め合い相互に受けとめなければ、効率優先の世の中に障害者が溶けこむことが難しい、と彼は語る。解決すべき障害者の社会的困難を無化して、障害者と健常者の境界をなくしてしまうのは問題である。しかし障害者という属性を、全ての表現に関係づける必要性については熟考を要する。芸術的側面と社会的側面の双方から慎重に意識を深めなくてはならない 世界的に有名な芸術家ゴッホや草間弥生が精神的疾患を抱えていたことはよく知られているが、彼らが障害者芸術の枠で語られることは殆どない。障害の有無にかかわらず、どの作家も自らが抱えるものを糧にした「個」の創造を行っているのである。周囲はその事実をまず受け止めなければならない。表現者よりも、表現されたものをどう受け止めるかという社会側の意識に問題がありそうである。そこでまず障害者芸術に関する歴史的経緯と、それに伴う社会的意識の変遷を簡単にまとめてみる。後半は福岡を中心にした障害者芸術に関係する活動をとりあげ、今後の方向性を見据える。
|
|||||||||
|
アウトサイダー・アートとアール・ブリュット 欧米における障害者の表現は、アウトサイダー・アート[3]またはアール・ブリュットと呼ばれることが多い。この場合のアウトサイダーという言葉は「社会から隔離されている」ことではなく、「正式な美術教育のアウトサイドにいる」という点が重要であった。アートとしての障害者の表現は「パラレル・ヴィジョン-二十世紀美術とアウトサイダー・アート」という展覧会を通じて、日本に広く知られることとなった。[4]これは一九九二年にロサンゼルス・カウンティ・ミュージアムで開催された展覧会で、翌年世田谷美術館に巡回している。日本における障害者芸術運動に大きな影響を与えた。 アウトサイダー・アートの概念は一九二二年、ドイツ、ハイデンベルグ大学付属病院精神科医師だったハンス・プリンツホルン著作の『精神病者の芸術性』という本から始まったものである。彼はヨーロッパ各地の精神病院から患者の精神状態を解釈するための作品を五千点以上も集め、これらに芸術的価値を見いだそうとした。第一次世界大戦後、機械技術崇拝の近代文明に疑問を呈した芸術家たちは、文明社会の枠組み外にあった視覚表現にひきつけられた。一九二四年に「シュルレアリズム宣言」を行ったアンドレ・ブルドンはこの本に掲載されていたアドルフ・ヴェルフリ(図一)などの作品を調査した結果、精神病患者たちが強制されずに制作された芸術を「健全な良心の宝庫だ」と絶賛するにいたった。マックス・エルンストはこの本からの引用と思われる作品も制作している。(図二)(図三)『精神病者の芸術性』を巡る状況は狂気への興味を喚起し、精神障害者の表現に対する再評価をもたらした。しかし障害者の疎外状況を改善するという意識はみられない。シュルレアリストたちは自らと精神障害者とは違うという姿勢をとった。サルバドール・ダリは「私と狂人との違いは、私が狂人ではないことである。」と主張している。 第二次世界大戦中、ナチスは精神病患者を遺伝的劣等人種として抹殺していく。一九三七年に「頽廃芸術」展が開かれ、モダン・アーティストらを卑しめるための比較材料としてプリンツホルン・コレクションが利用され た。大戦中は誹謗対象であった精神病患者の作品に、再度光をあてたのはジャン・デュビュッフェ(一九0一〜一九八五)であった。当時彼は画壇のエリート主 義を憎み、また独自の作風作りに悩んでいた。彼は『精神病者の芸術性』を入手した際、伝統の枠をはずれたところに表現の可能性があることを発見し、驚喜し た。一九四五年よりスイスにおいて精神病患者の作品収集を行う。(図四)デュビュッフェは伝統や評価の支配から解放されたこれらの芸術を「アール・ブリュッ ト(調理されていない、生の芸術)」と名付けた。一九七六年スイスのローザンヌにアール・ブリュット美術館がオープンする。ここでは美術的教育を受けずに自由に創作したこと自体が重視され、その境界における社会的差別意識は希薄である。西洋におけるアウトサイダー・アートやアール・ブリュットは先駆的・独創的な創造を強要する近代アー トシーンの重圧が必要とした「発想の源泉」である。 |
|
||||||||
|
日本における障害者芸術運動 独創性という観点から障害を捉えるアウトサイダー・アートの構造が、日本において発生しなかった文化的要因とは以下の二点である。まず障害者が社会生活を営む上でその芸術・芸能を経済的自立のための手段にする、という意識が歴史的に存在していたこと。次に西洋のような美術アカデミズムという社会的権威が存在しなかったため、美術的支配の枠外という概念が生じ得なかった点があげられる。 経済的自立のための手段として平安時代には芸能集団傀儡にカリエス、くる病、視覚障害者などが加わることもあった。鎌倉時代には平家物語を語り継ぐ視覚障害者の琵琶法師が存在した。江戸時代の検校制度によって、琴の教育に携わる視覚障害者たちもいた。[5]障害児を吉とする福子伝説や隣保制度の連帯責任などが障害者にプラスに働いた一方で、日本独特の差別意識である業病説も存在していた。法華経を書写していた女性をそしった罰として「白癩(ハンセン病)」になるという話があり[6]これはハンセン病などの感染病への恐怖と深刻な差別意識を生み出 した。一九三六年、ハンセン病患者である作家・北条民雄が隔離の現実を「いのちの初夜」(図五)によって世に問いかけている。[7]また、明治以降、富国強兵制度のもと、産業化と効率性が重視されるようになり、障害者は能力を持たないものとして社会から隔絶されることになった。 業病説と近世の帝国主義は、日本の障害者を心理的も社会的にも隔離する方向を生み出したのである。このような優性思想は日本に根強く残った。優生保護法の中で一九九六年まで様々な障害児の堕胎を認めてきたという歴史が日本にはある。このような背景のもと、障害を恐怖のまなざしや差別の対象とする意識に対して、社会運動的な要素が強くあらわれることになる。
|
|
||||||||
|
〈エイブル・アート〉
日本において障害者の芸術に注目が集まったのは九十年代である。この時期に台頭した多文化主義[8]も後押しして、障害をめぐる社会意識にアプローチする様々な芸術運動が起こった。そのひとつが社会的包容力を拡大しながら差別意識を乗り越えようとする「エイブル・アート」である。これは社会的目的に重きをおいて始まった活動であり、西洋の文脈とは異なる方向性をもっていた。 一九九三年「障害者芸術文化ネットワーク準備委員会」(後のエイブル・アート・ジャパン)が障害者芸術文化活動に関する実態調査を行う 。この研究結果がエイブル・アート・ムーブメントの基盤となる。エイブル・アートとは、一九九 五年、播磨康夫(財団法人たんぽぽの家理事長)が提唱した概念である。「人間に希望を与える新しい芸術」として障害者芸術の再評価を求めた。エイブル・アートは福祉施設間の連携を構築しながら全国的に活動を展開したため、障害者芸術に対する認知度を高めることに貢献した。エイブル・アートの最も大きな力は「ネットワーク」にある。孤立奮闘していた各福祉施設が情報共有によって改善のヒントを得、助成金獲得の機会を増やした。また作家活動を行う障害者たちが、展覧会への参加のチャンスに恵まれることとなった。近年は社会運動の域を脱し「個の発信」へと焦点が移りつつある。二00七年からエイブルート・カンパニーを設立し作品を商品化し、デザインとして使える仕組み作りを行っている。この活動は障害がある作家達の著作権を守ることにも繋がっている。
|
|||||||||
|
〈工房まる〉 福岡の福祉施設の中でいち早くエイブル・アートと連携し活動の場を広げたのは「工房まる」である。工房まるの魅力は、同時代のセンスを活かした軽快なアート感覚とデザイン力にある。(図六)施設長の吉田修一は、写真を専攻する大学生だった頃、作業所内の障害者をカメラの被写体にしたことが福祉と関わる契機となった。一九九七年に障害の種類や重度にこだわらず利用者を受け入れる無認可作業所として工房まるを開設。(二00七年にNPO法人格を取得)開設当時は陶器を中心に活動している「工房陶友」に影響をうけたという。後にエイブル・アートのネットワークの中で全国の施設の取り組みに学び、交流することで発表の機会を増やしていく。(筆者も二000年にエイブル・アート福岡フォーラム実行委員長として関わっている)中心人物達が若く、福祉の専門家でなかったことが逆に功を奏して、福祉の世界に風穴をあける。「かっこいい」「ゆるい」「おしゃれな」といった新しい感覚と発想を取り込みながら活動を展開している。開放的な施設の雰囲気もあり、様々な業種の社会人や学生たちが自然と集まる場となっていった。開所時は芸術活動を目的として集まった障害者集団ではなかったが、場と人の繋がりがクリエイティブな道を開き、芸術表現のクオリティをあげていった。近年は熊本現代美術館(図七)で作品展示を行っている。展示会場ではメンバーが来場者の似顔絵を描くなどの即興型パファーマンスも行う。工房まるのメンバーは「障害者」というカテゴリーではなく、個性をもつ「個人」として他者と関わる。そのコミュニケーションの力が工房まるの魅力を形作っている。ここで体験を共有した青年達が、他の福祉施設(「葦の家」「kara」等)に関わる契機を生み出しており、施設間の相互扶助・人材育成の場になっていることも秀逸である。
|
|
||||||||
|
〈和田千秋〉 障害者と健常者という二者対立の社会的認識に対して、新しい視点をなげかけた現代美術家が福岡にいる(図八)。「すべての人は障碍者である」提唱した和田千秋(一九五七年〜)である。彼は障碍児の親として障碍を受容する過程を作品化した作家である。(和田は〈障碍〉という表記をコンセプトの一部としている)[9]。いつ病気や事故で障碍を追うかもしれな いという意味で人はすべて潜在的な障碍者である、と彼はいう。高齢化社会という観点からも障碍を引き受けケアする立場になるという可能性は高い。和田は芸 術表現を通じて障碍に対する(主に健常者側の)意識を揺さぶっている。障碍の問題を自らのもの として思考する姿勢によって、自己を共同体の可能的一員とする意識が開く。和田は健常と障害が地続きである認識はもちろん、障碍と無関係な人間は皆無であるという強く鮮烈なメッセージを突きつけた。[10]
|
|
||||||||
|
〈工房しょうぶ〉 エイブル・アートが社会的活動やネットワークに重きをおくのに対して、欧米のアウトサイダー・アート(アール・ブリュット)のように作品性を重視する動きもあった。世界的な活動を展開している「工房しょうぶ」(鹿児島、一九八五年〜)である。代表・福森伸は「健常者とのスタンスの違いをみつめ、そこから始めていくという感覚の重要性」を 呈した。[11]この施設は、特に刺繍の分野で斬新な作品を生み出している。(図九)NUI・PROJECTとしてアメリカのクリエイティブグロースアートセンターや東京都庭園美術館で展覧会を行っている。色面が 立体として浮き上がるほどに差し込まれる針と糸。その行為とこだわりの集積と集中力が、みるものを圧倒する。これを福森は「〈縫う〉という行為そのものが 素材のもつ可能な限りの〈強いできごと〉を出現させている。それは作者が〈創り出す作品〉よりも〈創り出すための時間と行為〉に幸福を感じているからであ る」と表現している。属性に関係なく現代美術として通用する作品性の根拠はこの「強さ」にあるのではないだろうか。思想家ヴォルター・ベンヤミンは、芸術作品には「崇高な」「一回きりの」あるいは「不気味な」ものとしての「アウラ」が宿っていると考えていた。[12]彼らのファイバー・アートを前にすると、鑑賞者を押し返すようなアウラを放っていることがわかる。この他、音楽表現活動としてOTTO&ORABUという民族楽器を中心に結成したパーカッション・ヴォイスグループも所属している。健常者の特性である「揃えること」に対して、彼らは頑強に「ズレること」を守っているようだ、と福森は語る。甘えのない骨太な表現活動が工房しょうぶの魅力である 近年の工房しょうぶは、地域の人々とのコミュニケーションを鑑みた多種多様な活動を行っている。敷地内にはカフェ、そば屋、地域交流スペース(オムニハウス、二0一0年〜)があり、高齢者、障害者、子どもを中心に地域のつながりを広げるアートコミュニティーの場となっている。多様な福祉の垣根を越えて地域に開くというコンセプトは、富山の自宅開放型福祉施設「この指とーまれ」が一九九四年から実践している。福岡でも二00四年から「NPO法人エスタスカーサ」が取り組んでいる。
|
|
||||||||
|
〈JOY倶楽部アトリエブラヴォ〉 歯科医・緒方克也は治療に訪れる知的障害者によびかけて、音楽(一九九三年〜)とアート(一九九四年〜)の活動を始めた。これは通所授産施設「JOY倶楽部プラザ」[13]を設立する契機となり、「ミュージックアンサンブル」と「アトリエブラヴォ」の活動へと展開していく。主体的に部門を選択するため、アート部門に所属するメンバーのモチベーションとプロ意識は高い。アトリエブラヴォの特徴のひとつは、生活への視点が創作の基盤にあることである。当事者の社会的経験を広げ、世界観を豊かにするためにアートを手段とする。細かな 生活記録を残し、メンバーの今をスタッフが共有している。自立のための練習部屋には、公演に伴うホテル宿泊を想定してユニットバスが設置してある。筆やパ レットを洗うことは、箸や食器を洗う行為に繋がっている。自由に選択できるよう豊富な画材が準備され、メンバーは制作が終わると床を雑巾掛けする。逆説的ではあるが、創造よりも生活環境向上に注視していることが、主体的な創造を生み続ける要因となっている。メンバーの色使いは爽やかで、対象への愛とユーモアを感じる作風だ。個々の福祉状況のイノベーションは、作品の伸びやかさに反映する。(図十)バイクのスーパーカブを六十人の著名人がペイントしたLOVE CUB50プロジェクト(二00七年)に出品し明るい作風が好評を博した。(図十一)作品身体性を伴うライブ感覚もJOY倶楽部アトリエブラヴォの特徴のひとつだ。舞台での創作パフォーマ ンスに加え、福岡市内での壁画制作は十二カ所にのぼる。ライブペインティングを重視するのは、コミュニケーションを通じて社会に入り込み、周囲に想像力を 与えるためだ。外に飛び出して人と出会い、内面世界を共有し、属性ではなく「名前」で呼びあう契機をつくっている。
|
|
||||||||
|
〈アリヤ〉 福岡近辺の福祉施設の作品、商品を紹介する雑誌が『アリヤ』(図十二)である。二0一0年に電通が行ったフリー・ペーパー(マガジン)の調査によると(事業所数一二四五社が発行した約二億八千部数について)編集内容の中心となる項目に福祉をとりあつかったものは見当たらない。[14]福祉を内容の軸においたアリヤの取り組みは全国でも非常に独創的なのである。二00七年に初刊を発行し、現在一五号まで刊行されている。写真やデザインのクオリティが高く、古典的福祉観[15]を感じさせない。強いて言えば「オーガニック」「自然志向」といった若い世代が好む現代的傾向に近似している。アリヤは福祉関係施設と協力し、商品開発も行っている。編集長・藤野幸子は障害者の創造活動と経済活動を、雑誌を媒体にした「情報」を通じてダイナミックに繋いだ。「本当に知らせなければならないことを、ちゃんと知らせる」ことを彼女は重要視している。この決意はアリヤをソーシャル・ビジネス(社会的貢献を目的とした事業)の域に押し上げ、障害者の経済的自立を実質的に支えようとしている。[16] 各福祉施設は創造活動を経済活動に結びつける努力を続けている。しかし美術大学出身の卒業生達と同じく、創造活動のみで生活を営むことは難しい。福岡の「NPO法人花の花」は(書道を中心とした創作活動を行っている)農産物生産活動とオーガニックレストランを結びつける中で就労支援を行っている。このように創造活動一本ではなく「様々な事業を有機的につなげることで経済活動をまわす」という傾向は今後さらに発展していくだろう。当事者の生活上の困難が歴然として残っていることを忘れてはならない。障害者の保護者達が気にかけていることは、保護者亡き後の生活援助である。グループホーム[17]の必要性が叫ばれる所以である。障害者の現実的な福利や問題解決は、地域の想像力や理解に依る。そのために障害の有無に関係なく様々な立場の人間が出会う仕組みや〈場〉が必要である。アリヤの活動は、このような意識や情報が交差する〈場〉を紙面上に力強く構築しているのである。
|
|
||||||||
|
おわりに 以上、障害者芸術に関する歴史的経緯と、それに伴う社会的意識の変遷、福岡を中心とした具体的活動事例を俯瞰してきた。全体的な方向性として、関わりの中で創造活動が広がり、活動がさらに「個」と「個」のコミュニケーションを広げているという傾向がみられる。鑑賞者のみが想像力を喚起されているのではない。当事者もまた創造活動によって社会との接触が広がり、他者への想像力を押し広げている。コミュニケーションによって変化するのはどちらか一方ではない。 美学者・佐々木健一は芸術がいくつかの契機によって構成された複合体であるとした。技術(改造する力)・知(認識)・作品(美)・冒険的精神(快)という四つの契機に根ざすとし、常に現状を超えてゆこうとする精神の冒険性は他の契機を現実化し一体化する力として働くという。これらの契機に根ざし、美的コミュニケーションを指向する活動を佐々木は芸術と定義づけた。[18]これは美を媒介とし自己を他に対して共感させうる能力を根拠としている。感動を与えてくれるモチーフ(自然や動物、人)との出会い。失敗する経験や試行錯誤のプロセス、関わり、主体的な挑戦。その美的コミュ ニケーションの総体が芸術なのである。 こうした芸術の側面が、障害者問題を含む社会意識を揺さぶる可能性はある。しかし同時に、鑑賞者が傍観者として無自覚に障害者を他者化する危険性があることも指摘しておきたい。なぜなら障害者芸術の礼賛によって心理的な差別状況が解決されると、現実的な疎外状況や社会的困難まで解決されたような錯覚が起こるからである。自らと障害の間は地続きである。障害者の社会的不利益は「潜在的な自らの問題」なのである。(これは障害者に限らず震災被災等の問題にも通じる)これからは美的コミュニケーションによる心理的無境界性と、現実的な社会的側面の双方に目配りするバランス感覚が必要なのである。 最後に筆者は作家として、あえて付け加えたいことがある。芸術作品は、自分はここにいるという作家の叫びである。授産した生産物ではなく、精神的必然性を伴う能動的な行いである。経済的な見返りがない場合でも、作家は作らざるを得ないという情動に基づいて創造する。その情動の強さが作品の強さに通じる。自己の「言語化できないものの沈殿」を外化するというプロセスの中で、創造の情動はほぼ完結してしまうといってもよい。創造活動が何のためにあるのかと問われれば、自分が自分であるための、人間が人間であるための行いだと言うしかない。本論で紹介した作品の多くは、このような切実な状況の中で生まれている。美的なコミュニケーションとは「空気を読む」といった表面的な歩みよりではない。出会うことで自他の価値観や存在そのものが揺さぶられるものである。彼らの作品はラディカルに問いかけている。芸術とは何か。本物の作家とは誰か。そして障害者とは誰なのか。
|
|||||||||
|
[i] 想田和宏『精神病とモザイク』中央法規 二00九年 七六頁 [ii] 北島行徳『無敵のハンディキャップ』(文春文庫一九九九年)一0八頁 [iii] この用語は美術史家ロジャー・カーディナルが一九七二年に確定したものである。 [iv] モーリス・タックスマン、キャロス・エリエル編『パラレル・ヴィジョン-二十世紀美術とアウトサイダー・アート』淡交社 一九九三年 [v] 花田春兆「日本の障害者の歴史」財団法人 日本障害者リハビリテーション協会発行『リハビリテーション研究』第五四号 一九八七年 二〜八頁 [vi]妙法蓮華経普賢菩薩勧発品第二十八 [vii]川端康成・川端香男里・編『定本 北条民雄全集 上』東京創元社 一九九六年 [viii] マルチカルチュラリズムともいう。異なる文化を持つ集団が存在する社会において、それぞれの集団が対等な立場で扱われるべきだという考え方または政策をさす。 [ix] 「障害」はドイツの医学用語からの翻訳語はもともと「障碍」であった。『障碍の美術・現代美術のリハビリテーション和田千秋展』朝日新聞社 一九九六年 四頁 [x]脳性麻痺者であり、青い芝の会のメンバーだった横塚晃一による『母よ、殺すな』(すずさわ書店 一九七五年)の中で障害児とその親の関係について問題提起がなされている。脳性麻痺を患う子どもを殺してしまった母親に対して「減刑嘆願運動」が起こった。これに対しあるがままの「命」を認めよと横塚は主張した。障害は個性であるという考え方はここに端を発する。和田千秋のように、障害児の家族になったことを契機に新境地を開いた芸術関係者は多い。視覚障害者のための美術館「ギャラリーTOM」を作った村山亜土・治江等。福岡でも0歳児からの障害児を受け入れている音楽教室「MUSIC LIFE」を営むピアニスト花崎望はダウン症の子供(一昨年逝去)の親であった。 [xi]知的障害者施設しょうぶ学園工房しょうぶ 『季刊しょうぶ』冬号 二000年 [xii]ヴァルター ・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社 一九九九年 [xiii] 正式名称は社会福祉法人福岡障害者文化事業協会・知的障害者通所授産施設「JOY倶楽部プラザ」である。緒方克也が理事長をつとめている。 [xiv] 「二0一0年フリーペーパー・フリーマガジン広告費調査」電通 電通総研 [xv]米国の障害者研究者クロッグストン、ベス・ハラーの研究による用語 岩隈美穂「異文化コミュニケーション、マスコミュニケーション、そして障がい者」『現代思想 特集・身体障害者』青土社一九九八年 一九九頁 [xvi]きょうさ連全国大会in福岡ホームページ http;//kyosaren33・seesaa・net/ 二0一0年七月二十一日掲載文 [xvii]グループホームとは、病気や障害などで生活に困難を抱えた人達が、 専門スタッフ等の援助を受けながら、小人数、一般の住宅で生活する社会的介護の形態のこと [xviii] 佐々木健一『美学辞典』東京大学出版会 一九九五年 三一頁〜三五頁 |
|||||||||
|
知足 美加子 TOMOTARI Mikako (九州大学助教・国画会彫刻部会員) |
|||||||||