|
講演会「未来につづく道」
|
|||||
|
大地、生命、農業と芸術の融合による教育プログラム
|
|||||
|
(九州大学現代GPの一環として)→現代GPホームページ
|
→テープ起こし →講演会案内 →アンケート →ちらし(表) (裏)
 |
 |
|
普川容子氏
|
ハーブガーデン・プティール倶楽部内 講演風景
|
 |
|
→Design the Earth 設置風景
|
 |
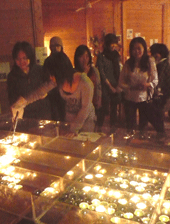 |
|
制作者(九州大学芸術工学部3年生)
|
WS参加者たち
|
|
普川容子講演会に参加して
(九州大学芸術工学研究院 知足美加子) |
| 普川容子氏は、深刻な世界貧困問題について、その根源にある債務の構造を鋭く分析し提示した。現地調査や正確なデータを元に、債務の不当性を指摘。その口調の静けさと誠意に参加者は次第に引き込まれ、深く問題を共有していった。
現在14億人の人々が1日1.25ドル以下で暮らす極度の貧困状態にある。そのうち8〜9億人の人々が飢餓に苦しんでいる。この格差社会を解決する方法には4つあるという。1)援助の増額、2)貿易ルールの改善、3)気候変動(温暖化等)をくい止める努力、4)債務問題の解決。日本は世界の債務の5割を貸し付けている債権国である。ODAは純粋な援助ではなく貸し付けである。債務を返済できない国に対しては「構造調整」が行われる。構造調整とは債務国に対して、関税をなくすこと、輸出を増やすこと(外貨獲得のため)、教育・医療への公的サポートを減らすこと、などを強いる。関税の問題によってハイチが決定的な農産問題に陥った例をあげ、日本も地産地消体制を整える必要性があるのではないか、と普川氏は提言した。 1970年代、オイルショックのために金融は滞った。その時、貸し付け先のターゲットになったのが途上国である。しかし貸し付けた公的プロジェクトの73%が持続的なメリットを生まない事業だったという。つまり債務による公共事業から、途上国の国民側は殆ど利益を得ることはなかった。(プロジェクトは外資系企業が請け負う場合が多かった)にもかかわらず、途上国の国民が税金によって債務を返済しなくてはならなくなったのである。普川氏は、債務による不当なプロジェクトの実態について言及した。公共事業だけでない。軍需につぎ込まれる債務は全体の30%を越える。紛争がさらに厳しい貧困状況をつくり出す。 債務は、金利、レートの変動に大きな影響を受ける。借りた元金の金額を返済していたとしても毎年増え続ける金利分を債務国が返済している、というケースも多い。また独裁政権が、個人的な利益のために債務を搾取する場合もあった。これらの事実から、債務の正当性について疑問視する世論がおこっている。実際、ノルウェー政府は自らの過ちを認め、債務帳消しを実行した。 日本人は自らが債権国であるという認識があまりに低い。特にアジア諸国と日本との債務についての認識には大きなズレがある。私達は自らの加害性を明確に認め、よりよき解決策を模索しなくてはならない 最後に普川氏が語ったキーワードとして「環境債務」という言葉がある。先進国がこれまで行ってきた途上国への環境破壊を債務として実数化すると、現在貸し付けている金額を越える。つまり債務帳消しどころか、先進国側が環境債務を途上国に支払わなければならない、と彼女は語った。 債務による社会構造によって、あまりに「命」が粗末にされている。普川氏の講演は未来への重要な提言である。参加者の心を強く動かし、講演後活発な質疑応答が行われた。 普川氏講演会の内容と、九州大学芸術工学部3年生のチームによるアート・プロジェクト「Design the Earth」の表現、会場の雰囲気がうまく調和し意義ある時空間を創り出していた。 2008年10月10日 講演会の記録は、3回分の講演会を合わせて報告書として作成する予定です |

10月10日18:30〜 |
普川 容子(ふかわ ようこ) 一橋大学法学部国際関係課程卒業。London University, School of African and Oriental Studies (SOAS) ディプロマ課程卒業。University of East Anglia(UEA), School of Development Studies 修士課程修了。エッソ石油財務調査本部勤務、NGO「�ヒ�ュ�ー�メ�イ�ン�・�イ�ン�タ�ー�ナ�シ�ョ�ナ�ル・�ネ�ッ�ト�ワ�ー�ク」事務局長代行、ジュビリー2000債務帳消し日本実行委員会広報担当等を経て、(特活)アジア太平洋資料センター理事。主な著書・論文に「トルコ人女性が向き合う二重の壁」(内藤正典編『トルコ人のヨーロッパ〜共生と排斥の多民族社会〜』明石書店)「米国/EU 遺伝子組み替えをめぐる貿易紛争」(月刊『オルタ』2004年2月号)「インド・ケーララ発 市民力 −IRTCの取り組み」(月刊『オルタ』2004年8/9月号)「GATS サービス貿易の自由化」(月刊『オルタ』2004年12月号)「IMFと世界銀行: 日本のかかわりを知っていますか?」(『NI-Japan』2004年3月号)『徹底検証ニッポンのODA』(共著、コモンズ) |