|
講演会「未来につづく道」
|
|||||
|
大地、生命、農業と芸術の融合による教育プログラム
|
|||||
|
(九州大学現代GPの一環として)→現代GPホームページ
|
→テープ起こし →講演会案内 →アンケート →テープ起こし →ちらし(表) (裏)
 |
 |
|
波平恵美子氏
|
ハーブガーデン・プティール倶楽部内 講演風景
|
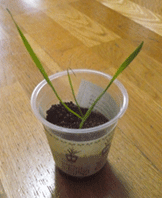 |
|
→Design the Earth
講演会参加者への「麦」のギフト |
|
波平恵美子講演会に参加して
(九州大学芸術工学研究院 知足美加子) |
|
本講演会は、波平氏の弛まぬ調査研究と鋭い洞察によって、「農」の概念に新しい光をあてるものとなった。 人類にとって農業の登場は非常に画期的であった。狩猟採集から農業中心の生活に移行することによって、人類は「予定する」「予測する」といった思考を獲得することになった。つまり先を考えて今を生きる思考及び行動パターンは、農業が人類に与えたものである。 カラハリ砂漠のブッシュマンは約20年前に狩猟採集から農業中心の生活様式になった。定住することにより人口が増え、労働時間が倍増した。農業は発展し、さらなる労働力が必要となった。日本における弥生時代にも同様の変化があったと推測される。農業はより多くの勤労、高度な計画性・研究を求め、この方向性が工業化社会の基盤を形成した。縄文時代であっても初歩的な農業は行われていた。弥生期に農業が大規模になるに伴い、政治的命令系統や組織化が生じた。パプア・ニューギニアにおける低地の熱帯雨林では、原始的農業に近いものが現在も行われている。 波平氏は明治20年代の農業についても聞き取り調査を行っている。この頃まで江戸時代の高度な農業技術(品種改良、病虫害駆除等)が残っていたという。例えば篤農家が数百樽の鯨油を遠方から取り寄せたという記録がある。これは鯨油を田に撒き害虫(ウンカ)を駆除する農耕技術が存在したことを示している。江戸時代には驚くほどの農書が書かれ、優れた技術は全国に伝搬され共有された。地域限定の品種も数多く存在し、各藩が大切に管理していた。 日本の農業にとって最も大きな打撃は天災ではなく「工業立国に転換したこと」であった。それまでは篤農、豪農、庄屋、大地主が存在し、私財を農業技術の研究に投じていた。しかし日中戦争以後、それらの私財は株に投じられるようになり農業に還元されなくなった。政府は徹底的に農家を冷遇し社会の工業化を急いだ。これによって専業農家は減り、農業のプロといわれる人々が姿を消していった。 工業化が与えたダメージとして、まず日本人の世界観(生命観)が変化したことがあげられる。死(枯)と再生(発芽)が展開する農地が減少したことで、日本人は死と生を感得することが難しくなった。生命観を基本とする生活観を失ったのである。また土壌が軽視されるようになった。以前は土をなめて状態を確かめるほどだったが、機械化によって日本人は土そのものに触らなくなった。さらに市場経済の急速な価格変動は、農業の時間軸とはかみ合わず悲劇的な結果をもたらす。 しかし波平氏は、日本はその風土と栽培品種の多さから、農業従事者が絶えることはないであろうと言う。農業は死と再生を一体化させてくれる。自らの人生を越えたタイムスパンを具体化し、身体化するのが農業なのである。日本人にとって重要な農業を活性化するためには1)中間マージンをいかに少なくするか、2)農機にかけるコストをいかに下げるか(農機に費用がかかり過ぎる現状の改善)という点を考慮しなくてはならない。 質疑応答の中で再度マウント・ハーゲン・ガーデンのことがとりあげられ、「人間は人間がいないと寂しい、という考えはいかに貧しいか。彼女達は決して孤独ではありません。いつでも土と話していると考えられます。」と波平氏は語った。土は死を含有しながら命を生み出していく。土と対話し向き合うことを忘れれば、人間は自らの命への洞察を失うのではないか。波平氏の言葉のひとつひとつが、とてつもなく大きな問いかけとなって私の心に刺さった。 2008年10月24日 講演会の記録は、3回分の講演会を合わせて報告書として作成する予定です |

10月24日18:30〜 |
波平 恵美子(なみひら えみこ) 1942年、福岡県生まれ。元・日本民族学会(現・日本文化人類学会)会長。お茶の水女子大学名誉教授。文化人類学専攻。九州大学教育学部卒業。テキサス大学大学院人類学研究科(1977年、Pf.D取得)。九州大学大学院博士課程単位取得満期退学。佐賀大学助教授、九州芸術工科大学(現・九州大学)教授、お茶の水女子大学教授を歴任。 日本文化論(日本民俗学)における「ハレ・ケ・ケガレ」という三項対置の概念を示した。主な著書に『病気と治療の文化人類学』(海潮社)『ケガレの構造』(青土社)『脳死、臓器移植、がん告知』(ベネッセ)『病と死の文化』『日本人の死のかたち』(朝日選書)『いのちの文化人類学』(新潮選書)『暮らしの中の文化人類学(平成版)』(出窓社)、編著に教科書として評価の高い『文化人類学』(医学書院)がある。 |