| 彫刻は時間を必要とするものである。制作する間に出会ったことを自分で確認するために、内省をこめて記していきたい。(2005年12月から) |
|
2月7日
|
やっと4本の粗彫りが終わったので工作工房に運ぶ。接合部分の調整をするために胴体を仰向けにしなくてはならない。手を貸してくださる技官の方々の存在にはいつも感謝する。
中司先生(農学部)が関わるプロジェクトの一環として寒立馬を取材できることになった。(2月後半)問い合わせをしたところ町役場の方が案内してくださるという。なんとありがたいことだろう。内なる願いが真実なら、現実が手をさしのべてくれることがある。 子供のために借りてきたビデオに私の方が釘付けになってしまった。西部開拓時代に服従しなかった馬の物語である。馬の脚の動きをだいぶ勉強させてもらった。柴田善二先生の恩師・石井鶴三氏が木曽馬を制作中、歩きながら馬の脚の動きをまねたという。後ろからその姿をみかけた先生は「馬のことをずっと考えているんだな」と思ったそうだ。先生もカバを制作中、なぜかテレビでカバのシーンをよくみかけたらしい。対象を思う心はその情報をひきよせる。人間の心の不思議だ。 |
  |
|
2月9日
|
「寒立馬(かんだちめ)」とは、もともとマタギ(東北山岳地帯の狩猟を生業とする人たち)が厳寒の中で何日も動かずにたたずむカモシカみて、そうよんでいたそうだ。南部馬の血を受け継ぐ東通村の野生馬が、短歌の中で「東雲に 勇みいななく寒立馬 筑紫が原の 嵐ものかは」と詠まれた。それから「寒立馬」とよばれるようになったという。
脚の接合部分に径20mmの鉄芯をいれる行程に入る。鉄棒の切断、バリ取り、治具作り(ドリル刃を垂直に入れるため)など段取り作業が続く。技官の方に手を貸していただいて、逆さ向きの脚を胴体に何度もあわせては降ろす。いつになったら四つ足の状態で作業できるだろう、と待ち遠しいが、彫刻は下部から、見えないところからあせらず進めていくしかない。 |
   |
|
2月14日
|
先週末はクレーンと玉掛けの免許習得。今週後半は卒研・修論発表会でまとまった時間がとれない。そんな気持ちもあり、つめて作業をしているうちに昼食をとるのを忘れてしまった。最近の昼食はシリアル栄養食品ばかりだ。
尻尾の量と長さがたらないので接ぐことにした。落下防止のため、ほぞを入れる。脚の接合面にドリル刃の中心をとり、治具をビス留めする。穴をあけ、穴の中の木屑を手動ドリルでこさぎ出す。この作業が8面ある。手がしびれてしまい、最後は力が入らなくなった。案の定、最後の面は垂直がずれていて、二度手間がかかる。集中力が持続する範囲で休憩をとらないと、結局遠回りをすることになる。いつものことだ。 |
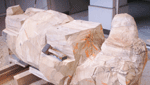  |
|
2月21日
|
下腹部など、脚がついたら手が入りにくい部分をある程度彫る。
いよいよ脚を接ぐ段階に入る。接合部分に木工ボンドを塗る。左官屋さんのようだ。胴体はクレーンに吊った状態で塗る。 鉄心の入った脚を4本同時に組むのは、至難の業だ。技官の方々には本当にお世話になり申し訳ない。 それでも4本足で自立した彫刻をみると、沸々とうれしさが込みあがってくる。と、同時にやらなければいけない部分がドッと目に入ってきた。 明日から3日間、青森の下北半島に寒立馬を取材に行く。九州生まれの私は、東北の冬の厳しさは想像がつかない。どうなることだろうか。 |
 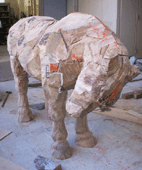 |
|
2月27日
|
22日から青森県下北半島東通村の海岸に向かう。そして実際に寒立馬に出会う。それは言葉にできないほどの感動だった。顔をすりよせる馬を抱きしめた感触が忘れられない。人間のコントロールの外にいるこの馬は、迎合せず恐れない。雪も吹き飛ばす冷たい海風の中、静かに立っている。その静けさは、こちらの命をひたすら肯定してくれているようだ。 そのようないきものに触れることが、これほど心を揺さぶるのかと自分でも驚く。詳しくは寒立馬取材のページへ |
 |
|
2月28日
|
冬の寒立馬は妊娠中の馬が多く、想像以上にお腹が大きかった。また尻尾も長く力強い。用意していた尻尾の接ぎ木をかえなくてはならない。
馬に惹かれるようになったのは、幼少期に「野生の子馬」(都井岬の馬)という絵本を持っていたからだと思う。私は小児喘息持ちだった。床に伏せっている間はこの本を読み、何度も模写した。海岸沿いを自由に走り回る馬の姿は、病気の私に励ましや夢を与えてくれたのだ。今回、寒立馬がいる海岸をみて鮮明に絵本の風景が蘇った。私の心の中に生き続けていた「希望」に出会った気がした。 |
 |
|
|
→続きは3月のページ
|