
九州大学芸術工学部では、キャンパス内の主要施設におけるネーミングライツパートナーを募集しております。
●対象施設
デザインコモン、多次元デザイン実験棟
詳細はこちらをご覧ください。
*2025年11月5日更新


九州大学芸術工学部では、キャンパス内の主要施設におけるネーミングライツパートナーを募集しております。
●対象施設
デザインコモン、多次元デザイン実験棟
詳細はこちらをご覧ください。
*2025年11月5日更新




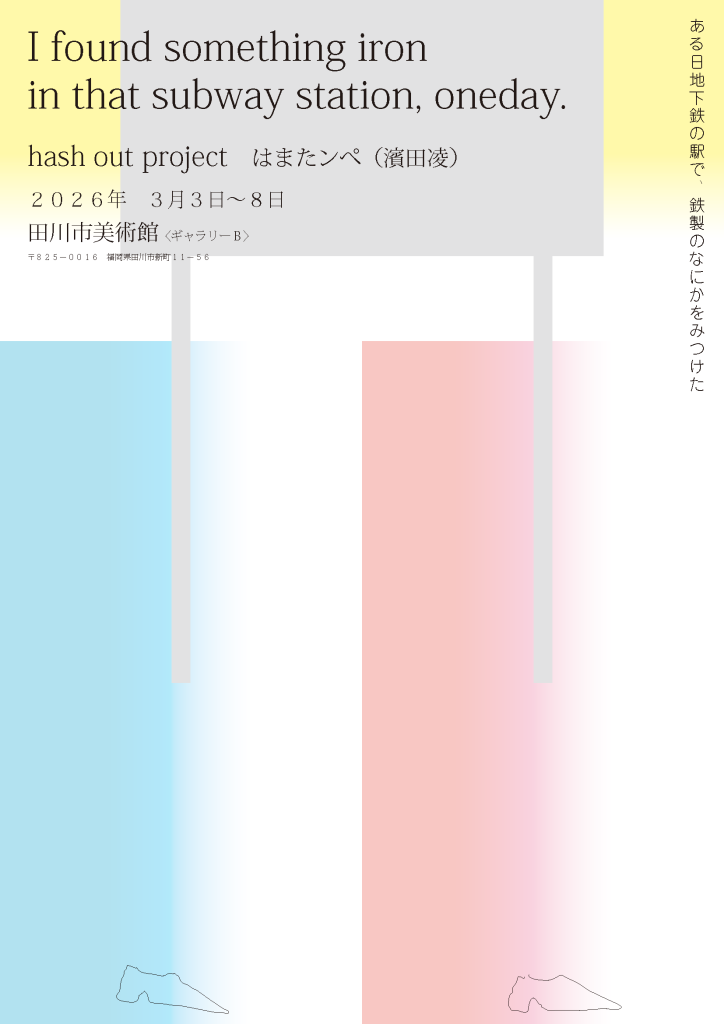
| 参照リンク |
|---|
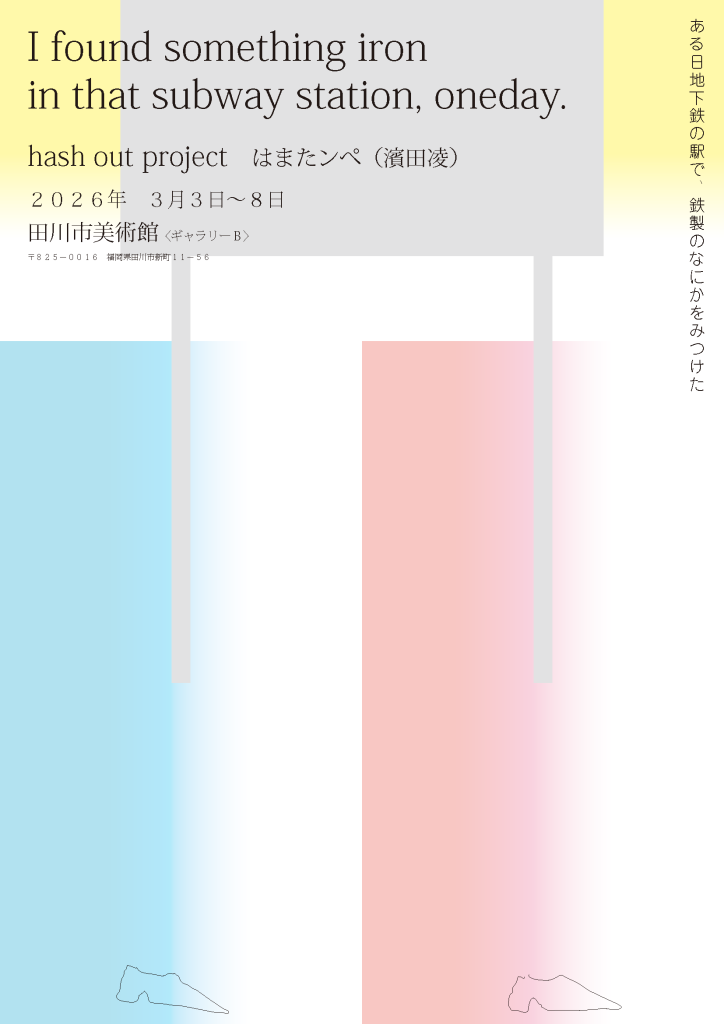

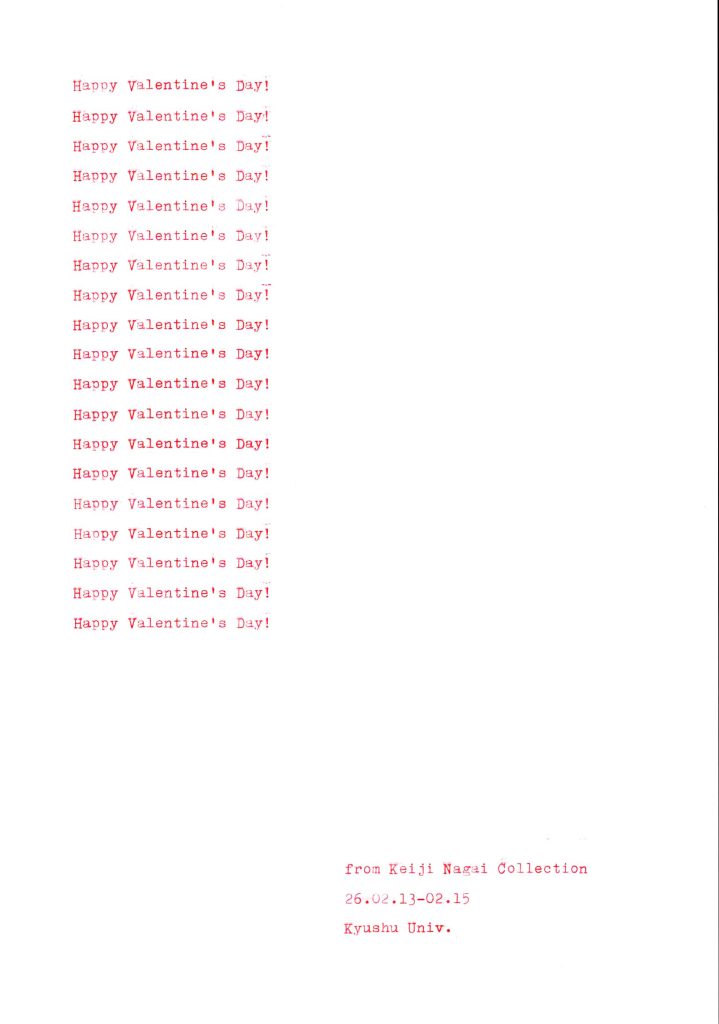
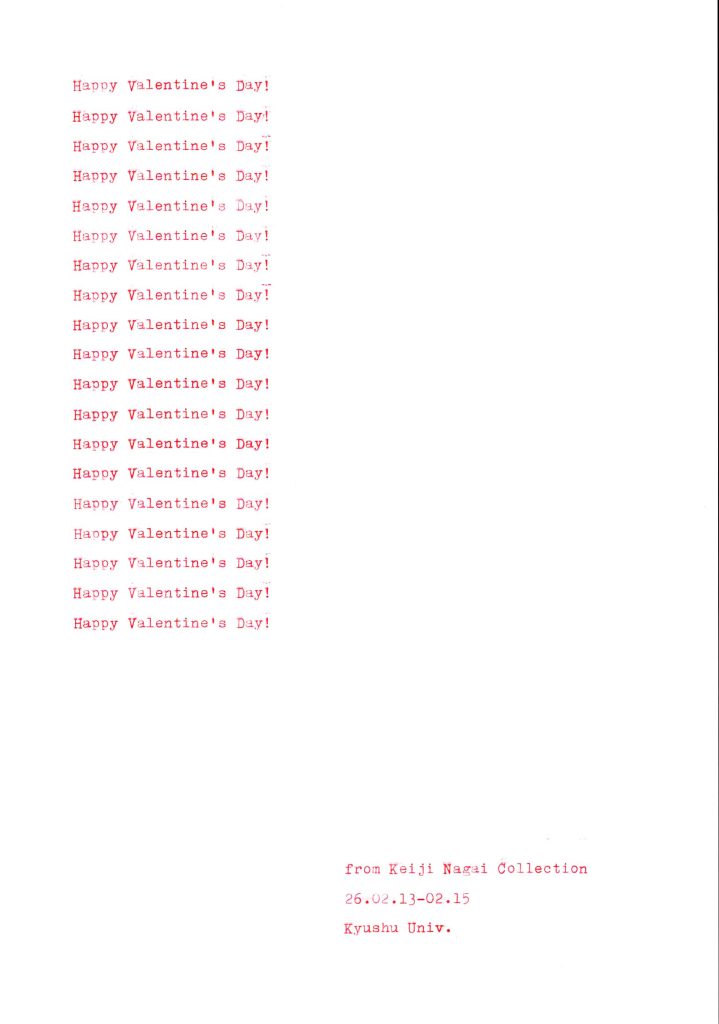

本プログラムは
3日間にわたり、レクチャー、展覧会、コンサート、そして最終日のシンポジウムを通して、サウンド・アートにおける芸術実践およびキュラトリアル実践の批評的かつ実験的アプローチを提示します。歴史的視座を現代における実践の課題や今後の展望と接続しながら、音楽、パフォーマンス、美術、メディアアート、科学技術、さらには政治的言説にまで広がる多様な実践の射程からサウンド・アートを考察します。開催概要
▪会期:2026年2月18日(水)–20日(金)
▪会場:九州大学大橋キャンパス
▪使用言語:英語(Q&Aは英語および日本語)
▪助成:文化芸術活動基盤強化基金「クリエイター等支援事業(育成プログラム構築・実践)」、JSPS科研費(課題番号:23H00591、23K17267、24K03533)
レクチャー:サウンド・インスタレーション・アート|
▪講師:Carsten Seiffarth
Ariane Beyn:ドイツ・ベルリンおよび日本・福岡を拠点に活動する美術史家、キュレーターである。2023年より九州大学大学院芸術工学研究院にて講師を務めている。2008年から2018年まで、DAADアーティスト・イン・ベルリン・プログラムの美術部門代表およびdaadgalerieのディレクターを歴任した。2008年にはアートフェア「abc art berlin contemporary」のアーティスティック・ディレクター、2006年から2007年にかけてはサンフランシスコのCCAワティス現代美術研究所の客員キュレーターを務めた。近年の主な展示やパブリック・プログラムには、『Beyond Migration』(コルカタ・ゲーテ・インスティトゥート、2022年/ヨハネスブルグ・ゲーテ・インスティトゥート、2023年)、『Readings from Below』(Times Art Center・ベルリン、2020/21年)、『Why an Archive?』(Arsenal 3・ベルリン、2020年)、および『Lawrence Abu Hamdan: Walled Unwalled』、『Teresa Margolles: Sutura』、『Sung Hwan Kim: And Who Has Not Dreamed of Violence?』(いずれもdaadgalerie・ベルリン、2018年)などがある。



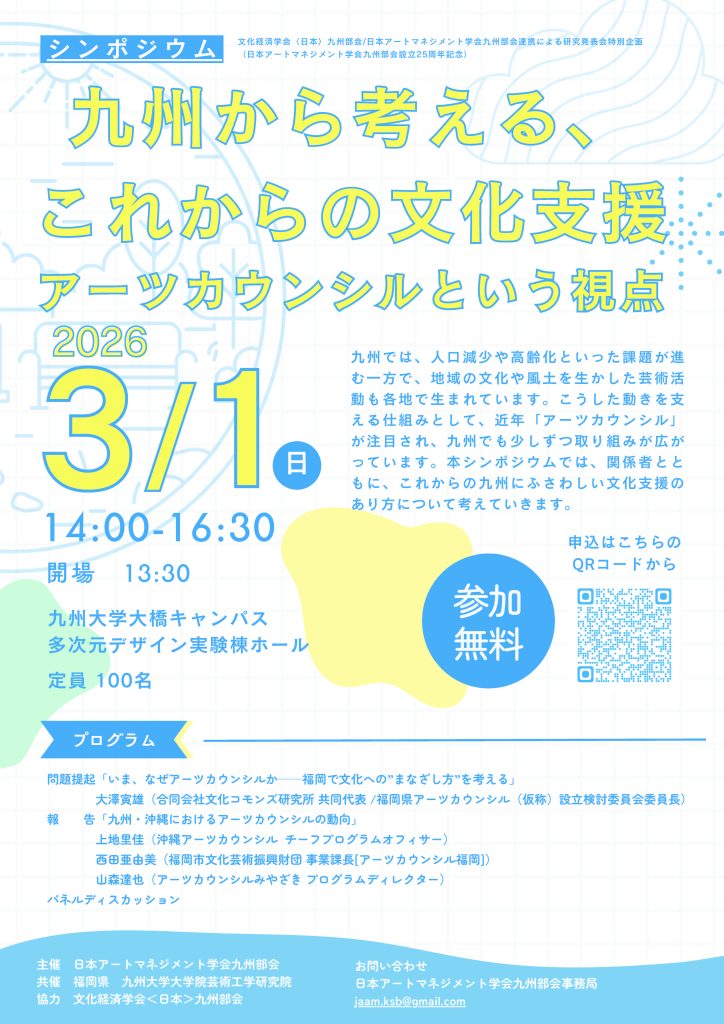
芸術工学研究院が協力し、文化経済学会〈日本〉九州部会/日本アートマネジメント学会九州部会連携による研究発表会特別企画(日本アートマネジメント学会九州部会設立25周年記念)として、シンポジウム「九州から考える、これからの文化支援──アーツカウンシルという視点」が大橋キャンパスで開催されます。
九州は、豊かな文化と歴史を有する一方で、人口減少や高齢化など、深刻な社会課題を抱えています。近年は、地域の風土や文化資源を生かした独自の芸術活動が各地で展開され、新たな文化創造の可能性も広がっています。
こうした中で、芸術の多様な表現を尊重しながら社会課題に応答する仕組みとして、「アーツカウンシル」が注目されています。英国で生まれたこの制度は、日本各地で導入が進み、2012年には東京都と沖縄県で始まりました。その流れは九州にも広がり、2019年に宮崎県で設立され、佐賀県や大分県でも同様の趣旨による仕組みが整えられています。
本シンポジウムでは、九州各地で芸術文化支援に携わるアーツカウンシル関係者をパネリストに迎え、人口減少社会を前提とした九州独自の文化支援のあり方や、将来に向けたアーツカウンシルの可能性について考えます。
本会を通じて、九州ならではの持続的な文化支援モデルを描き出す契機としたいと考えています。
▪日時:2026年3月1日(日曜日) 14:00〜16:30 開場 13:30
▪会場:九州大学大橋キャンパス 多次元デザイン実験ホール
▪対象:研究者、アーティスト、文化政策担当者、アーツカウンシル関係者、自治体職員、一般参加者
▪参加費:無料
▪プログラム:
14:00-14:05|開会挨拶 主催者からの趣旨説明、登壇者紹介
14:05-14:30|問題提起:
大澤寅雄(合同会社文化コモンズ研究所 共同代表/福岡県アーツカウンシル(仮称)設立検討委員会委員長)
「いま、なぜアーツカウンシルか──福岡で文化への”まなざし方”を考える」
14:30-15:15|報告「九州・沖縄におけるアーツカウンシルの動向」
上地里佳(沖縄アーツカウンシル チーフプログラムオフィサー)
西田亜由美(福岡市文化芸術振興財団 事業課長[アーツカウンシル福岡])
山森達也(アーツカウンシルみやざき プログラムディレクター)
各パネリスト 15分×3
15:15-15:25 休憩
15:20-16:20|パネルディスカッション
モデレーター大澤寅雄+パネリスト
16:20-16:30|閉会 主催者
▪お申し込み:以下のフォームからお願いします。
https://forms.gle/BqCLznxPoHGFPiA47
▪お問い合わせ:日本アートマネジメント学会九州部会事務局
jaam.ksb@gmail.com
▪主催:日本アートマネジメント学会九州部会
▪共催:福岡県、九州大学大学院芸術工学研究院
▪協力:文化経済学会<日本>九州部会
| 添付ファイル |
|---|
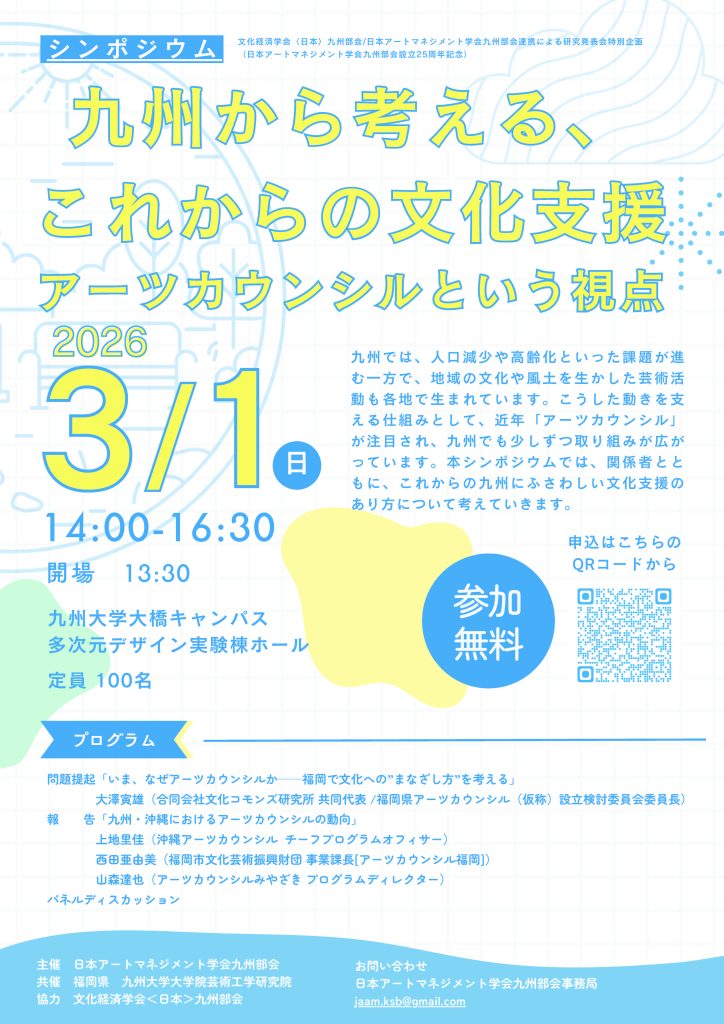

九州大学Webサイトの「芸術工学研究院 研究紹介」ページに、メディアデザイン部門 森本 有紀准教授の「創造を支えるCG研究―メディア表現からものづくりまで―」が掲載されました。
下記参照リンクよりぜひご覧ください。

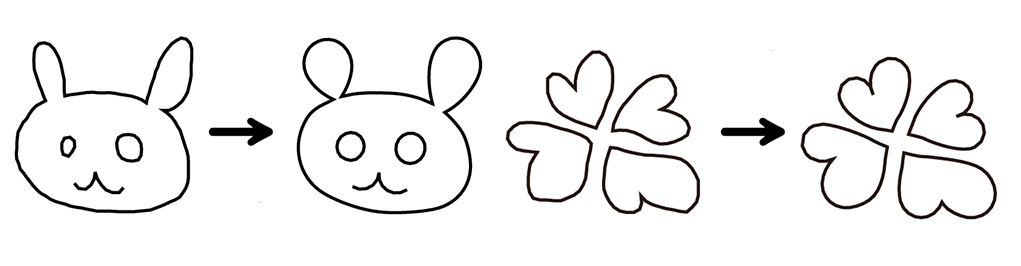

令和7年度卒業予定者の研究の集大成として、卒業研究展示会及び発表会を実施します。
どなたでもご覧いただけますので、ぜひご来場ください。
※開催日時や場所は、各コースや内容により異なります。詳細は添付のファイルをご確認ください。
◆日時
2026年2月12日(木)~15日(日)
◆場所
九州大学大橋キャンパス
◆入場料
無料
| 添付ファイル |
|---|


| 添付ファイル |
|---|

九州大学芸術工学部芸術工学科では、令和10(2028)年度以降の募集人員を変更します。
詳細は添付ファイルでご確認ください。
| 添付ファイル |
|---|
令和8年度の九州大学芸術工学部・大学院芸術工学府の科目等履修生・聴講生の募集を行います。
希望される方は入学案内をご参照のうえ期日までに出願書類を提出してください。