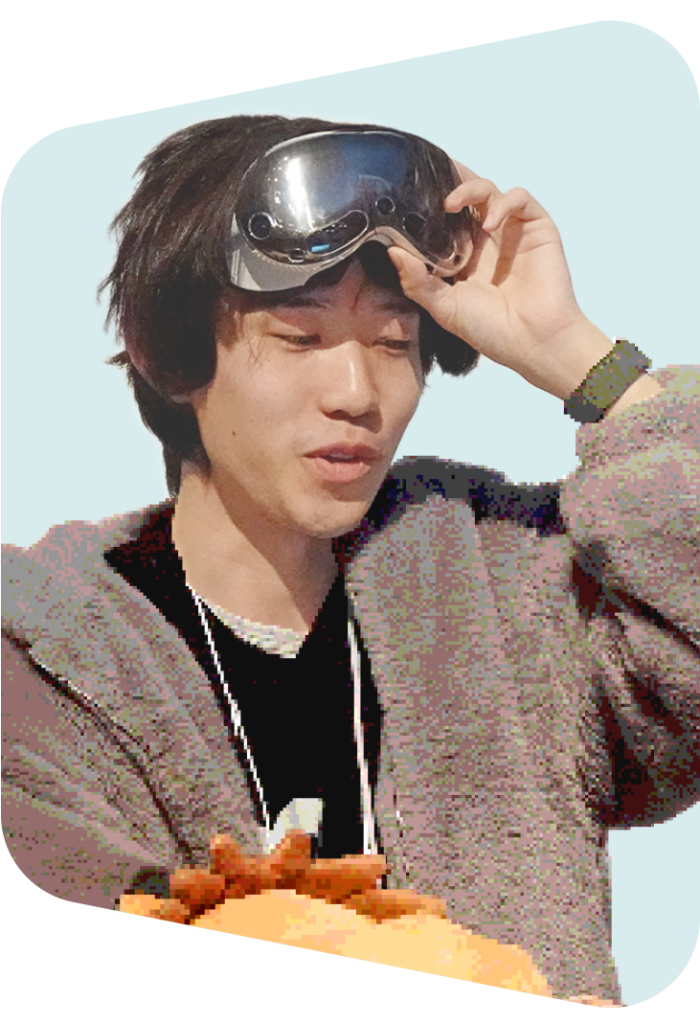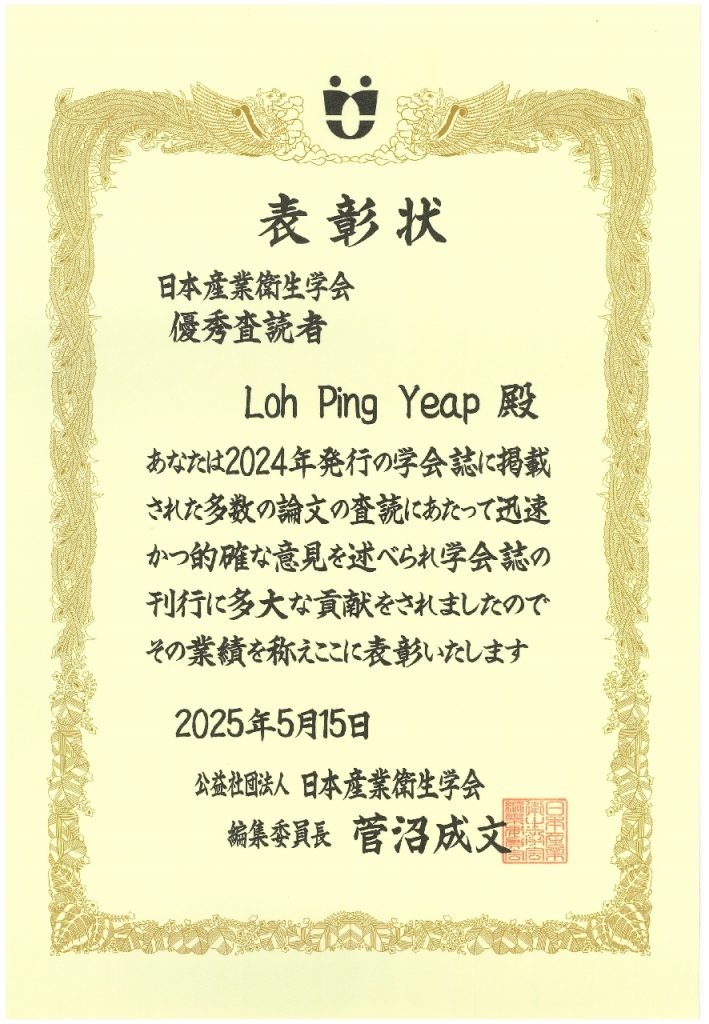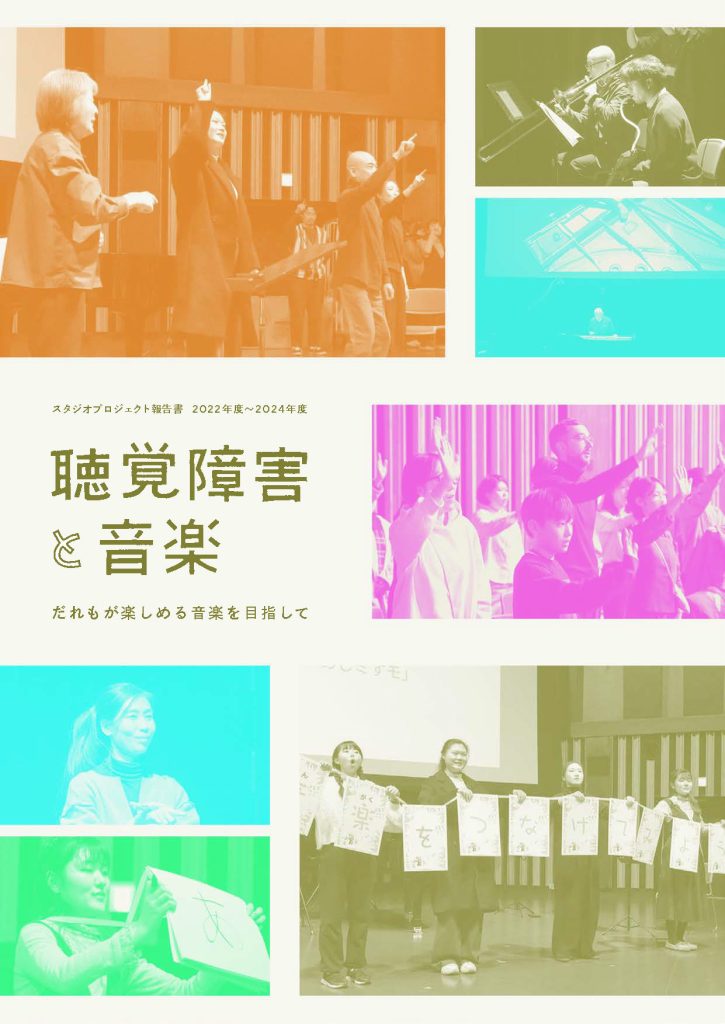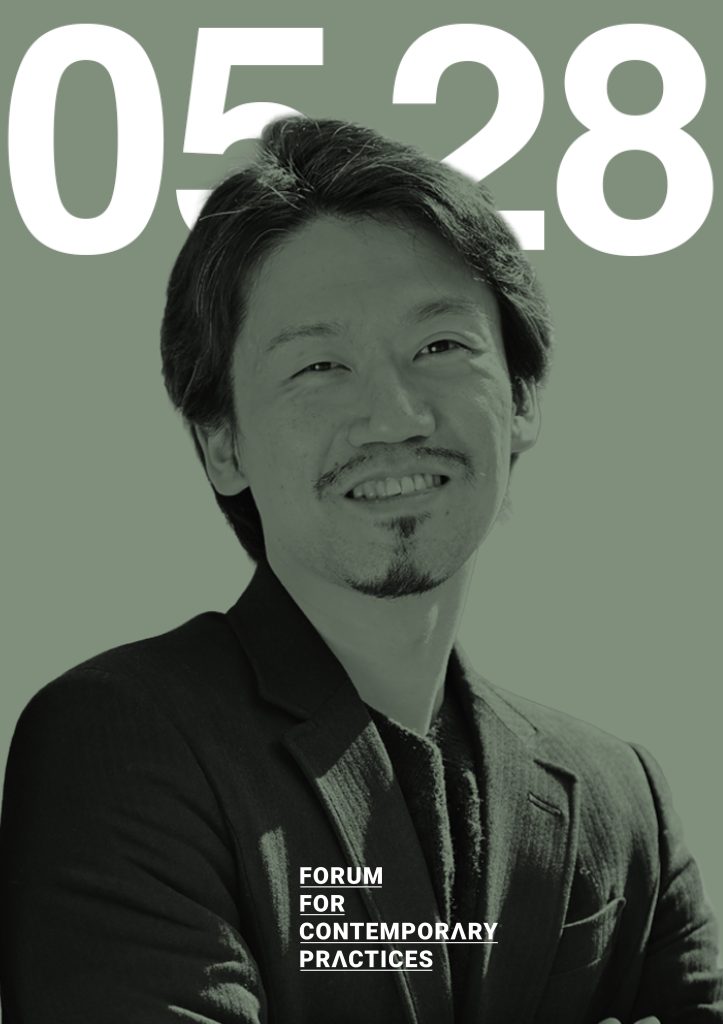九州大学総合研究博物館の公開展示「博物の森で遊ぼう」内で、芸術工学部特別展示として、「カリーナ・ニマーファル ≪非同時的なモノたち:帝国と環境≫」展を開催中です。
▪会期:2025年5月17日(土)〜6月15日(日)の土・日曜日(全10日間)10:00〜16:00
▪会場:九州大学箱崎サテライト(旧工学部本館1階146室)
▪入場料:無料
▪主催:科学研究費助成事業 基盤研究(C)「大学博物館におけるアート・インターベンションに関する理論調査と展示実践」(課題番号:24K03582 / 研究代表者:結城円 九州大学)
▪協力:九州大学総合研究博物館/九州大学大学院芸術工学研究院/オーストリア連邦芸術・文化・公務・スポーツ省/遊花遊月
芸術工学研究院の招へいにより、オーストリア人のアーティスト、カリーナ・ニマーファル氏が、能古島のアーティスト・イン・レジデンス「遊花遊月」の協力のもと、2025年2月から3月にかけて約2か月間福岡に滞在し、九州大学総合研究博物館のコレクションを調査しました。その成果が、二部構成のアートプロジェクトとして結実しました。
第1部は、2025年3月に大橋キャンパスで開催された展示です。博物館に収蔵されていた歴史的な木製家具をキャンパス内のギャラリースペースに移設し、デザイン、林業、環境史、帝国主義、物質的な知、超歴史的な展示実践、展示戦略といったテーマを含む資料とともに展示を行いました。
プロジェクトの第2部は、現在、九州大学総合研究博物館にてご覧いただけます。館内に、“カフェのような読書室”を出現させるアート・インターベンション(芸術の介入)を行っており、本作は、林業、生物多様性、そして第二次世界大戦前後の日本の木材貿易の歴史に関する大学コレクションを出発点としています。
本展では、大学コレクションを新たな視点で捉え直すアーティストによる語りのテキストを中心に据え、アーティスト自身の調査や制作プロセス、芸術と科学の関係性についての考察などが織り込まれています。さらに、それらのテーマやモチーフは、展示されている書籍や資料の中にも再発見することができます。ぜひ時間をかけて、ご自身の興味に導かれるままに、多様な資料を手に取ってご覧下さい。
最終日・6月15日(日)に予定されている、九大博物館展示室内でのカリーナ氏による朗読パフォーマンスイベントにつきまして、実施時間が以下のとおり変更となりました。
【変更前】13時、14時、15時の3回実施予定
【変更後】11時〜、14時〜の2回実施
アーティスト紹介|カリーナ・ニマーファル(Karina Nimmerfall)
ベルリンとケルン(ドイツ)を拠点とするビジュアルアーティスト・教育者。ドキュメンタリー手法とスペキュラティブなアプローチを融合させ、彫刻インスタレーションや言葉とともに、写真、コンピューター生成画像、映像表現などの形態を織り交ぜた作風をもつ。これまでに、カメラオーストリア(グラーツ、オーストリア)、MAKセンター・フォー・アート・アンド・アーキテクチャー(ロサンゼルス、米国)、BAWAGコンテンポラリー(ウィーン、オーストリア)、ブカレスト・ビエンナーレ3、第8回ハバナ・ビエンナーレ(キューバ)などで国際的に作品を発表。また、2018年のアルフリート・クルップ・フォン・ボーレン・ウント・ハルバッハ財団の「ドイツ現代写真フェローシップ」をはじめ、数々の賞を受賞している。