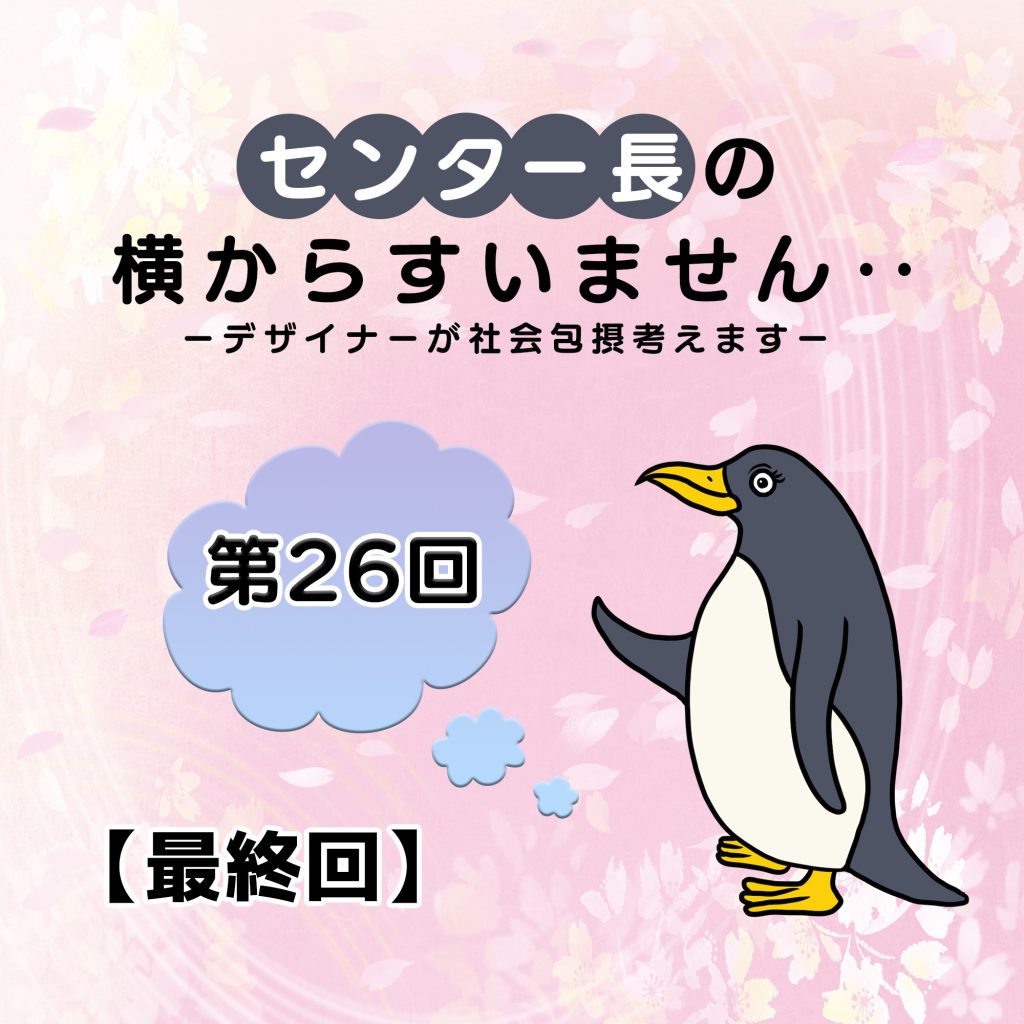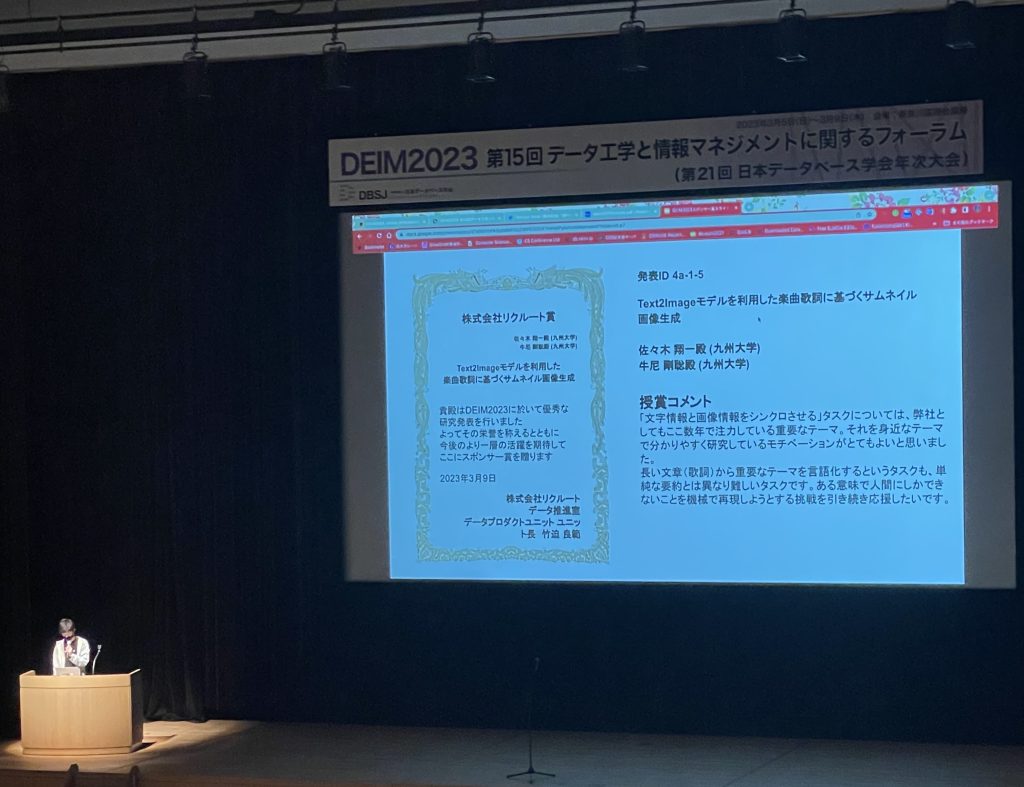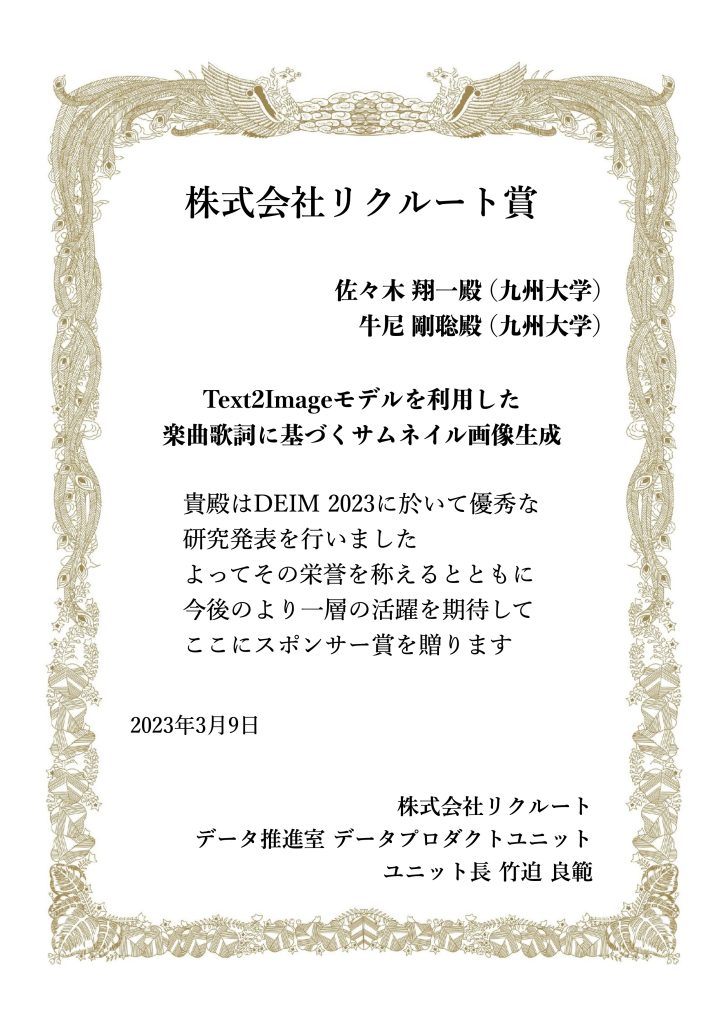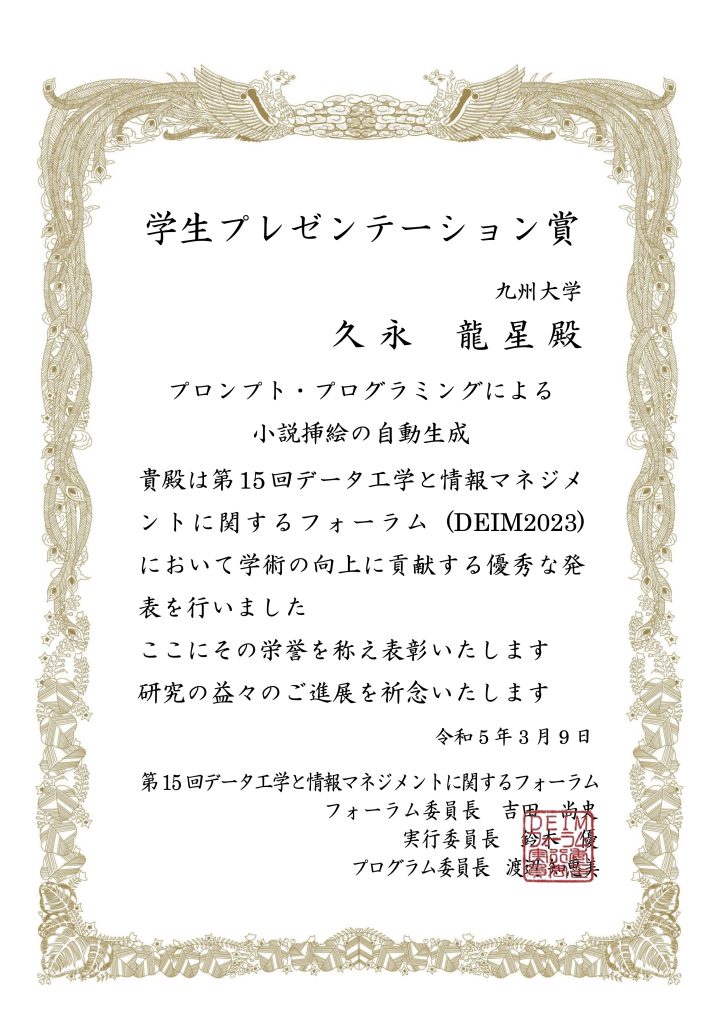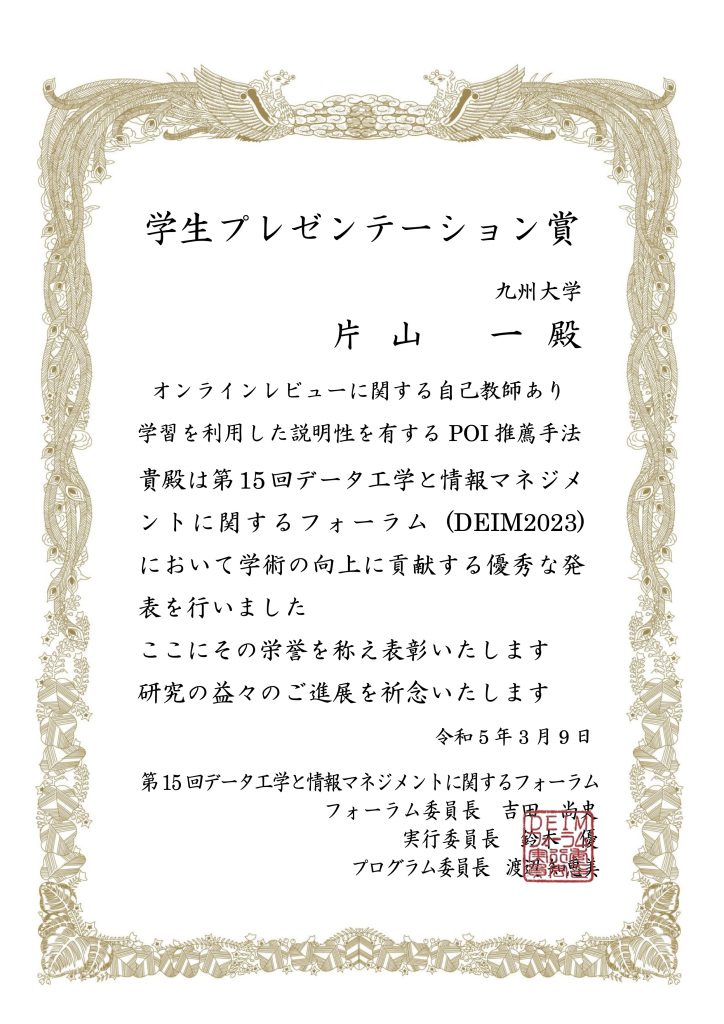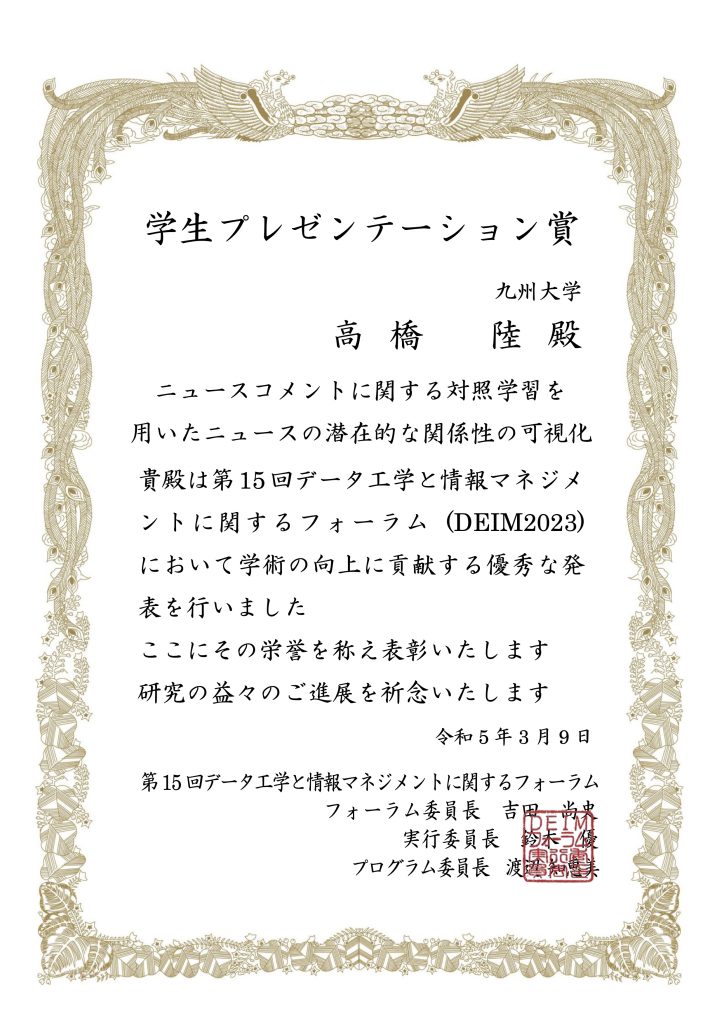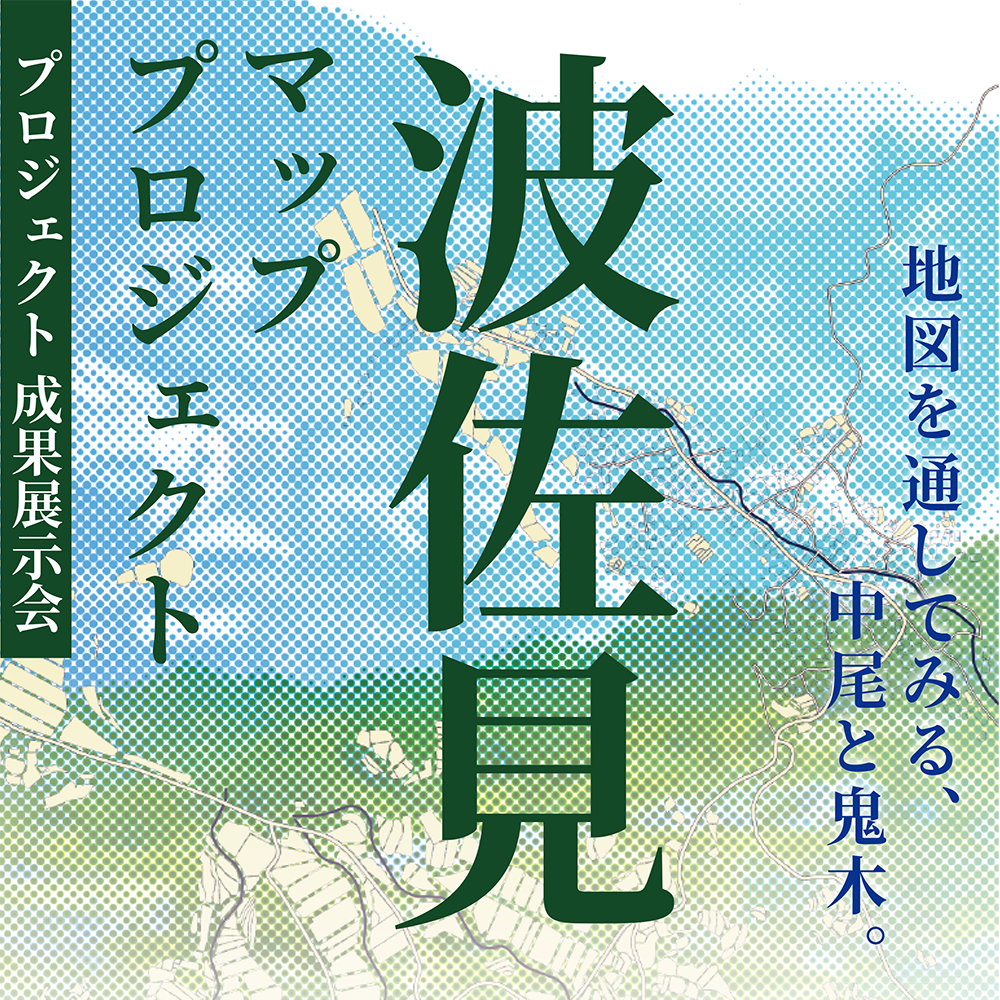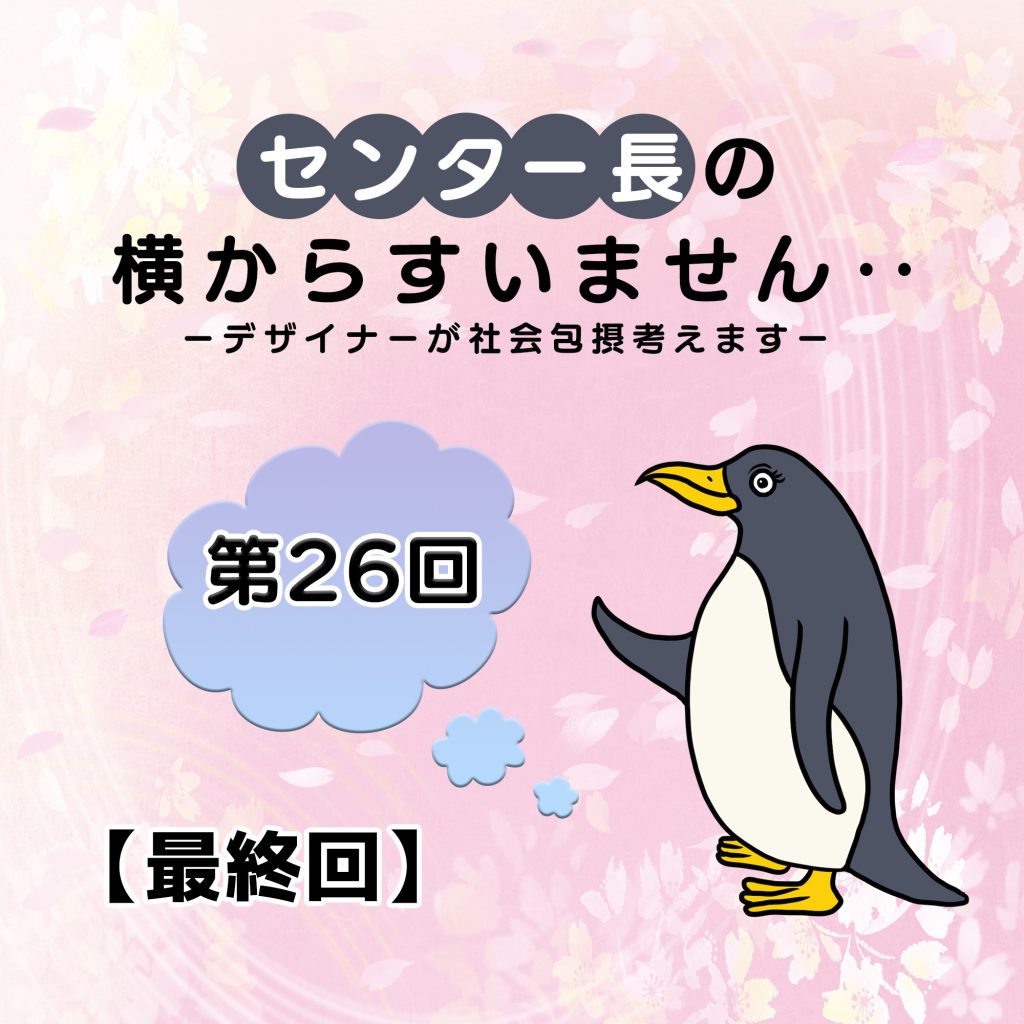
全26回のコラムでは、ジェンダー、子育て、障害、外国人など多方面の話題に触れながら、社会包摂とデザインについて考えてきました。
また、毎回掲載しているアンケートは、集計・分析の上、ご報告させていただきます。今からでもぜひご回答下さい。
コラムでは毎回、「リーガル・デザイン・ディクショナリー」として、関連する法律やルール、用語を紹介してきました。ぜひ、関心あるトピックのコラムを今一度ご覧いただき、その分野にどのようなルールが関わっているかも見ていただきたく思います。
私たちの身近なあらゆる場面に、様々なルール(法律や、明文化されていない慣習なども含む)が関わっています。多様な人々が共に生きる包摂的な社会を築こうとする際、これらのルールを避けては通れません。
「困っている人がいて、その困り事を解決したいが、既存のルールが壁となる」という場面は多々あるでしょう。その場合、そうしたルールがいつ、どんな目的で、どのようにつくられたのか、よく知らねばなりません。また、ほかにも複数のルールが関わっているかもしれませんし、逆に「困り事を解決するのに役立つルール」があれば、それを使うことも有効でしょう。ときにはルールを変えたり、既存のルールを廃止する、あるいは新しいルールをつくる必要も出てくると思います。
そのような「社会包摂とリーガル」について、DIDI では2023 年度も引き続き考察を深めていきます。
コラムの連載は完結しましたが、特別号や時評は時々発信していきます。引き続き、よろしくお願いします。