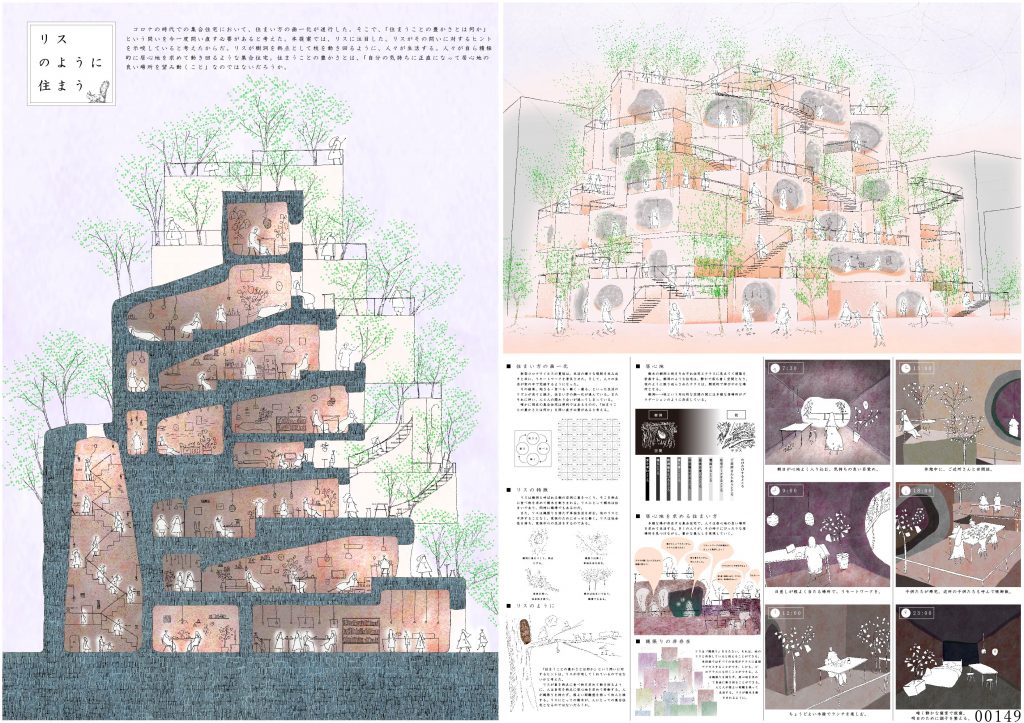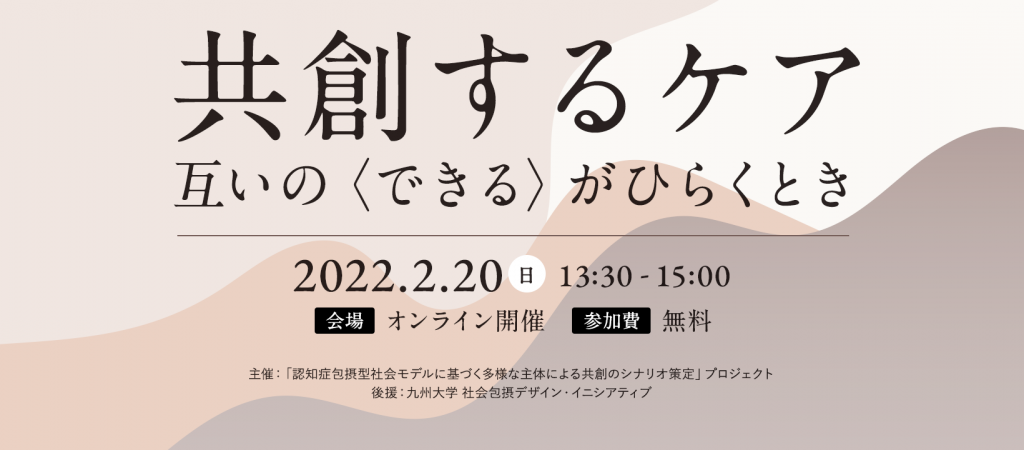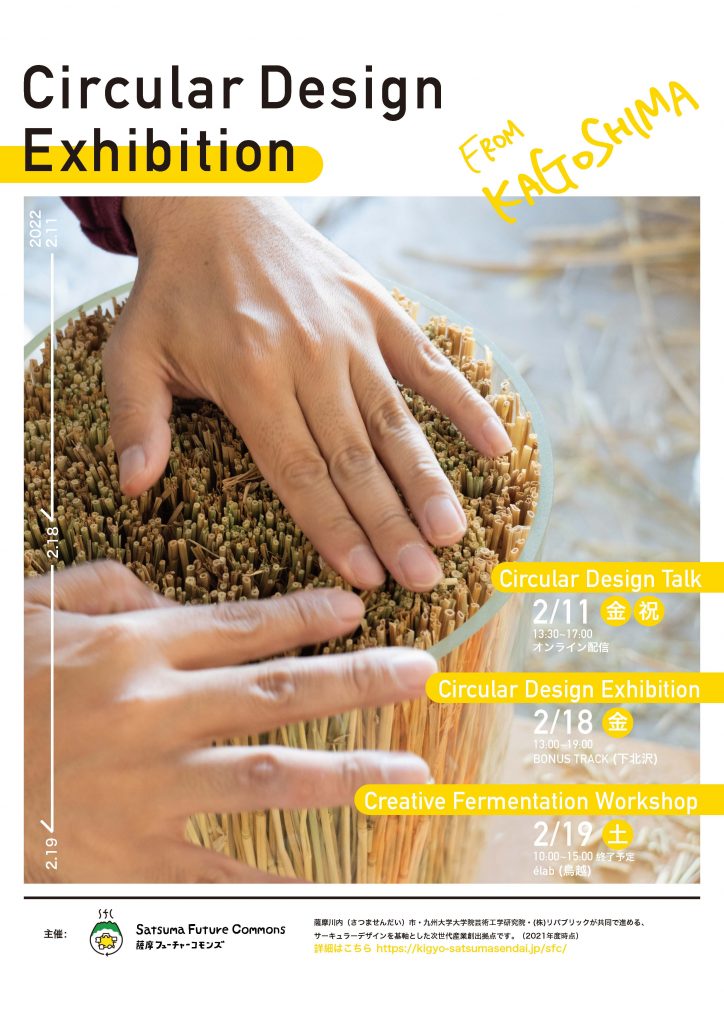社会包摂デザイン・イニシアティブでは、認知症ケアに関する産学官民の共同研究プロジェクトに取り組んでいます。
2020年10月より、認知症にまつわる人と人の関係性を変え、新たな価値を共創する仕組みを社会に実装すべく、当事者と介護者を交えた「共創的アート活動」がもたらす効果の検証、研究を進めてきました。2年間の研究期間で、認知症包摂社会の実現へつながる「共創的アート活動」の実装シナリオを策定することを目指しています。
本シンポジウムでは、認知症当事者と介護者のあいだに立ち起こる「共創」的コミュニケーションについて、医療介護施設での即興演劇を用いた活動ケースをもとに、本研究開発事業の中間報告を行います。あわせて、関連事例として『旅のことばー認知症とともによりよく生きるためのヒント』の紹介も交え、これからの認知症当事者とのコミュニケーションについてのパネルディスカッションを実施します。
————
日 時:2022年2月20日(日)13:30〜15:00
会 場:オンライン会議ツール zoom 上にて実施
参加費:無料
受講者:認知症の方の潜在能力を引き出すコミュニケーションを理解し、身につけることに
関心がある方ならどなたでもご参加いただけます
・ 認知症介護に関わる関係者や研究者
・ 認知症に関連するサービス開発に携わる関係者やアーティスト など
主催:「認知症包摂型社会モデルに基づく多様な主体による共創のシナリオ策定」プロジェクト
*本研究開発活動はJST、RISTEX、JPMJRX20A1 の支援を受けたものです。
後援: 九州大学大学院芸術工学研究院 社会包摂デザイン・イニシアティブ
お申込み:下記の申込みフォームにご入力ください
(事前に、開催日当日のZOOMミーティングID等をお知らせいたします)
実施概要:
13:30〜15:00(90分)公開シンポジウム
[進行] 堀田聰子(慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 教授)
▶︎当プロジェクトの概要紹介
—内田 直樹(医療法人すずらん会たろうクリニック院長)
▶︎事例1:当プロジェクトによる「共創的アート活動」についてのご報告
—中村美亜(九州大学大学院准教授/九州大学 社会包摂デザイン・イニシアティブ)
▶︎事例2:『旅のことば:認知症とともによりよく生きるためのヒント』活用事例について
—岡田誠(認知症フレンドリージャパン・イニシアチブ〈DFJI〉共同代表理事/富士通株式会社フィールド・イノベーション本部フィールド・イノベータ)
▶︎パネルディスカッション:両事例から探る認知症当事者とのコミュニケーションについて
————
【本事業について】
「認知症包摂型社会モデルに基づく多様な主体による共創のシナリオ策定」について
JST(国立研究開発法人科学技術振興機構)における戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発)にて令和2年度に採択されました「認知症包摂型社会モデルに基づく多様な主体による共創のシナリオ策定」として、以下目標に向けた取組みを行うプロジェクトです(事業期間:2020年10月〜2022年9月)。
【プロジェクトの目標】
本事業では、認知症包摂社会の実現に向けて、認知症にまつわる人と人との関係性を変え、新しい価値を共創する仕組みを社会に実装することを目指します。
そのために、認知症の方々が関わる場(例:介護施設やビジネス開発の場等)に「共創的アート活動」を導入することで、「支援するーされる」という関係性を超えて、認知症の人と支援者等との対話から新しいサービスが創出されるための方法・プロセス・評価基準を明らかにすべく、研究を進めています。
【主な研究参画・協力機関】
・医療法人すずらん会 たろうクリニック
・福岡市 保健福祉局 高齢社会部 認知症支援課
・九州大学 大学院芸術工学研究院
・ラボラトリオ株式会社
・NPO法人ドネルモ