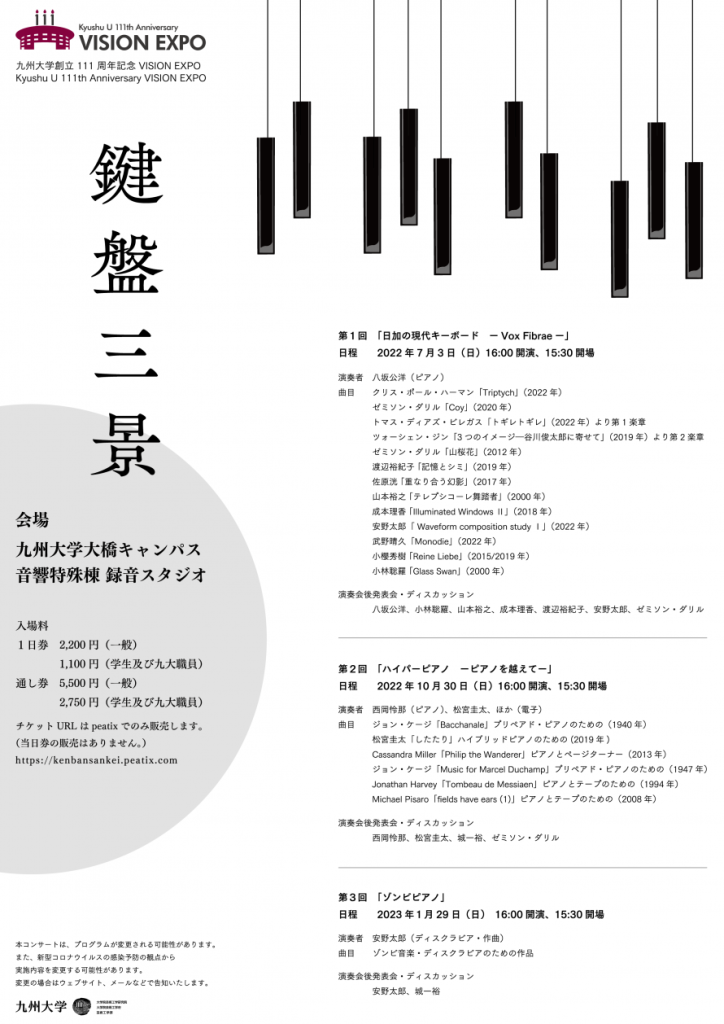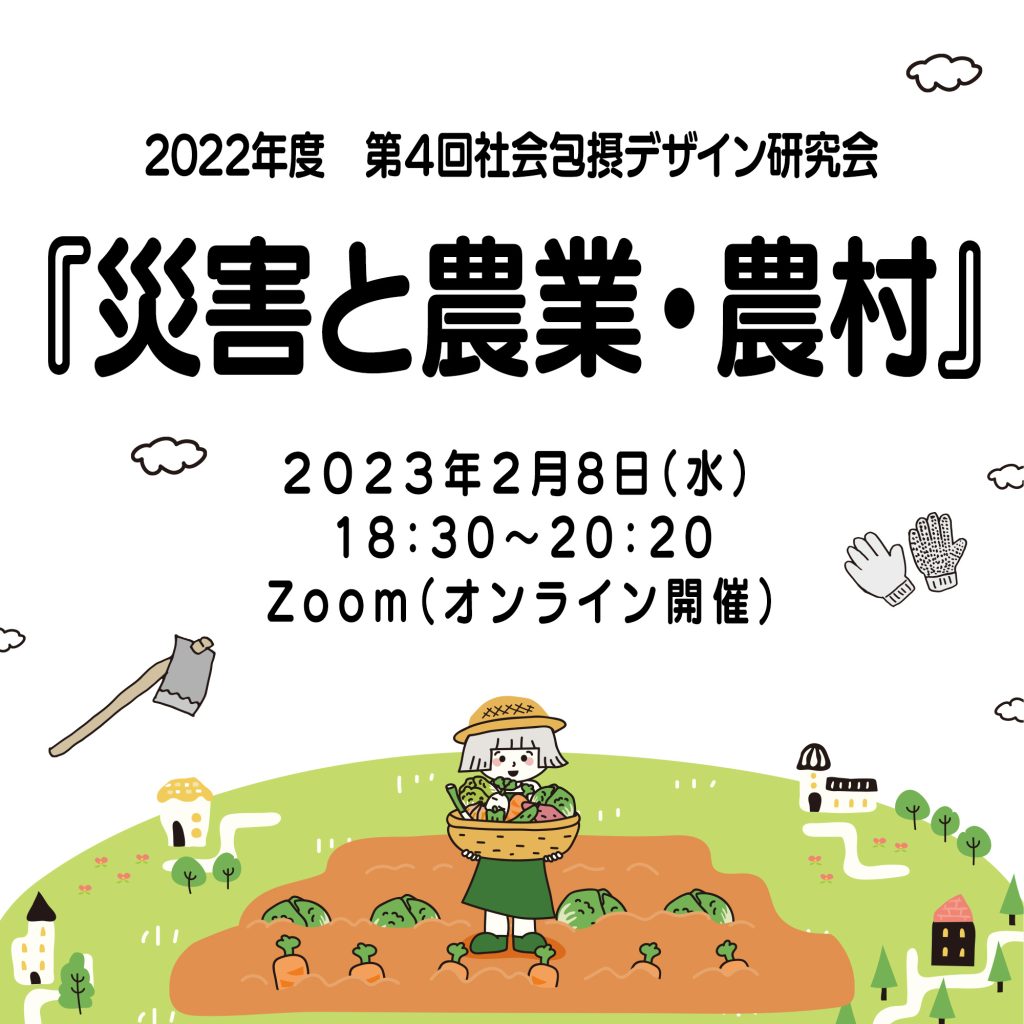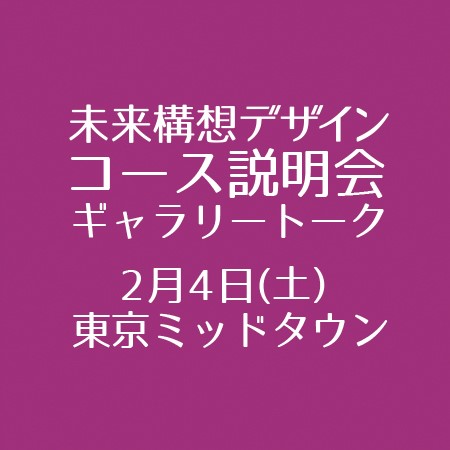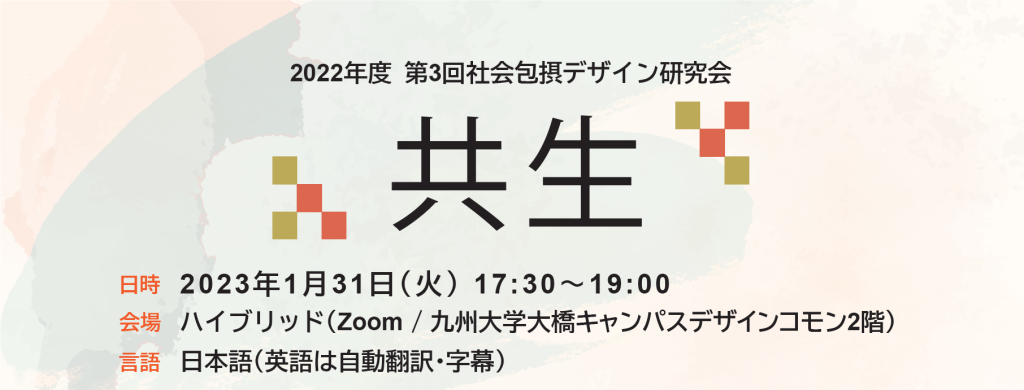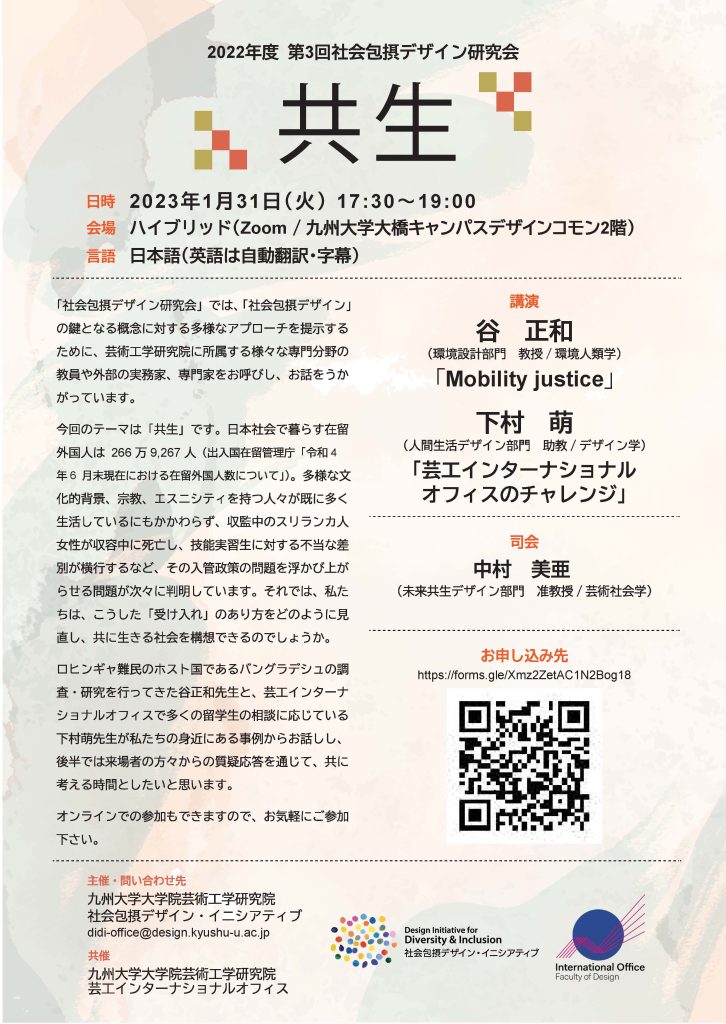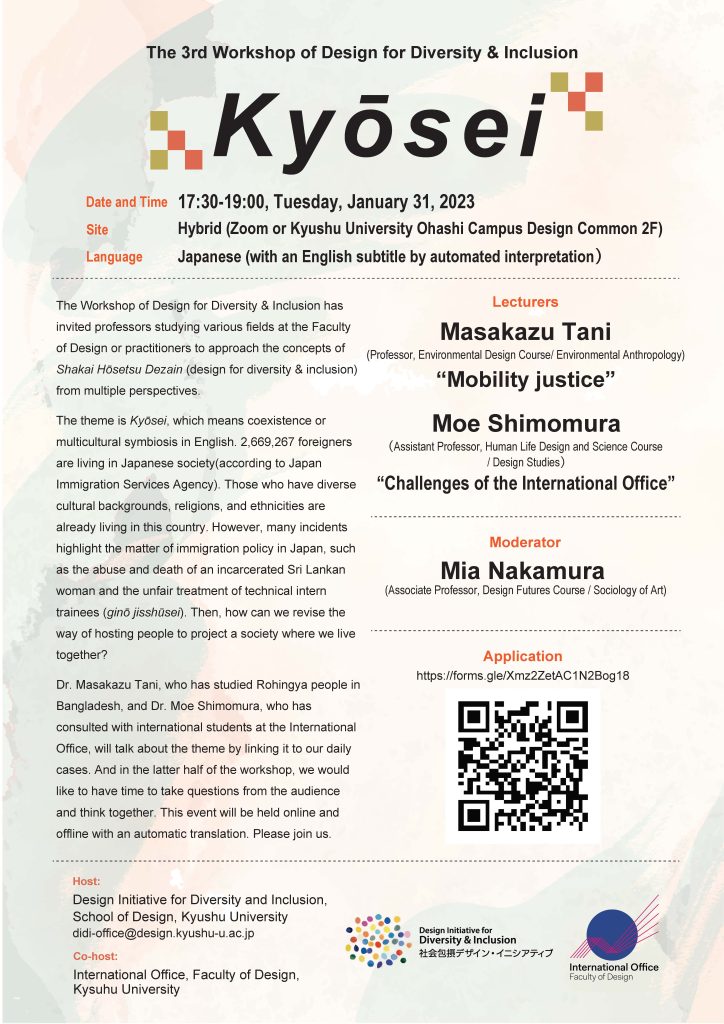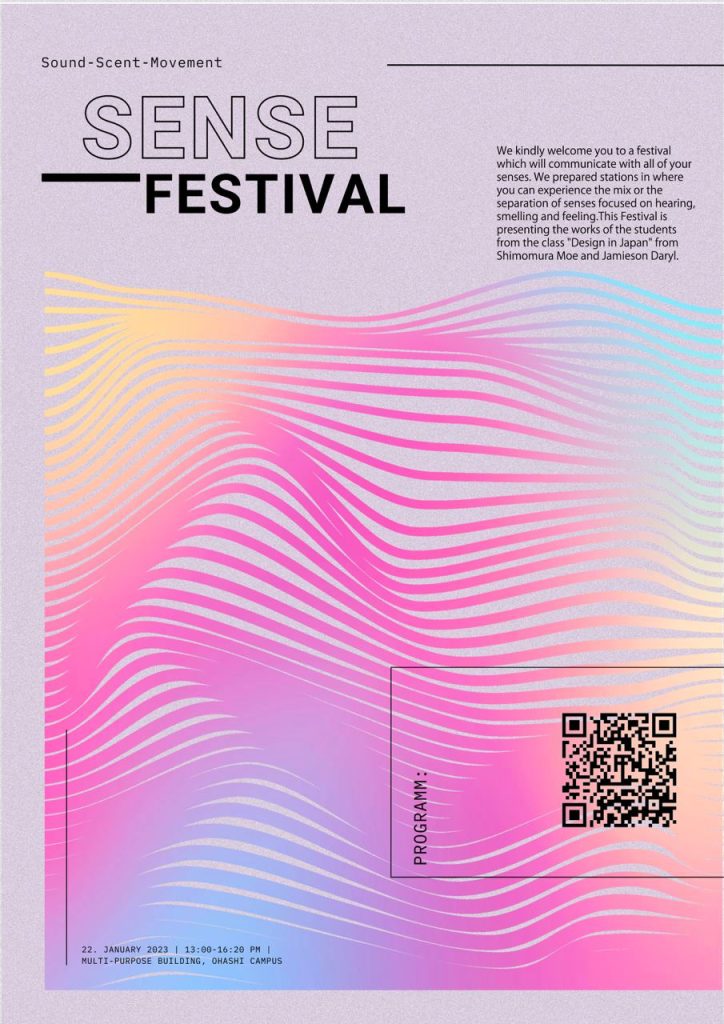ヴェンデリン・ファン・オルデンボルフ上映会
■日時2023年1月19日(木)19:00〜21:00
■場所九州大学大橋キャンパス 多次元デザイン実験棟
■参加費(入場料)無料
■主催九州大学芸術工学研究院
令和4年度大学改革活性化制度「日本デザインを創造し国際発信できる人材育成のための教育プログラムの構築」
令和3年度大学改革活性化制度「メディアアートによる科学・技術の芸術表現への昇華を通した価値の可視化プロジェクト」
■共催芸工インターナショナルオフィス
■申し込みフォームhttps://forms.office.com/r/fxsWYr3iLg東京都現代美術館で開催中のヴェンデリン・ファン・オルデンボルフ個展『柔らかな舞台』(2月19日まで)に際し、九州大学大学院芸術工学研究院では、ファン・オルデンボルフの映像作品2点の上映会と、作家とのQ&A(英語、日本語逐次通訳付き)を行います。
ヴェンデリン・ファン・オルデンボルフは、現代芸術作家として20年以上にわたり映像作品や映像インスタレーションを手掛けてきました。彼女の作品では、シナリオではなく、撮影の場で起こるプロセスが中心に据えられています。そのプロセスとは、公開撮影というかたちで、参加者がライブパフォーマンスや即興での対話によって脚本を共同制作することにあります。
この上映会では、個人的な物語と公共空間、そしてその歴史的文脈との関係を浮き彫りにする2つの作品を上映します。音楽家、アーティスト、活動家、そして理論家が、フェミニズム、人種差別、ポストコロニアル理論を、スポークン・ワード、詩、音楽パフォーマンスで体現しています。
「From Left to Night」2015年
♦ビデオ・インスタレーション(上映版)、カラー、サウンド、32分。
♦言 語 :英語、日本語字幕
♦ロケ地 :Joe Strummer Subway, Red Bus Studios, Paddington Green Police Station
(イギリス、ロンドン)
♦委嘱作品: The Showroom(イギリス、ロンドン)
「From Left to Night」では、ロンドンのパディントン近隣から集められた、一見つながりのない人物・場所・出来事・テーマ・歴史が2日間の撮影で交差し、6人の出演者・3つの場所・その出演者達が持つさまざまなテーマや知見がつながっていきます。
出演者は、ロンドンを拠点とする2人のヒップホップ・アーティスト、政治学者と心理学者(いずれもブラジル人)、オランダのヒップホップDJ、The Showroomのキュレーターです。テーマは、2011年のロンドン暴動などの都市の緊張から、新しいフェミニスト理論や人種理論、ミュージックビデオ、1960年代の建築、そして出演者とそれらとの個人的な関わりまで多岐に渡ります。
「Hier.」2021年
♦映像作品、カラー、サウンド、27分
♦言 語:オランダ語、日本語字幕
♦ロケ地:Museum Arnhem(改修工事中に撮影)(オランダ、アーネム)
♦委嘱作品:Sonsbeek 20➜24(オランダ、アーネム)
保存修復中のアーネム美術館(オランダ)において2019年に制作された「Hier.」では、女性たちによる音楽、詩、対話を通して、ハイブリディティ、トランスナショナリティ、ディアスポラといったテーマを扱っています。その中で、出演者だけでなく、アーネム美術館という場所もまたその表現の一部となっていきます。
撮影が行われたアーネム美術館は、19世紀後半に「Outdoors Club」として建設されました。このクラブは、アーネムにあった紳士クラブ「Groote Sociëteit」の会員になるための社会的地位を持たない植民地からの移民が設立したものです。
ヴェンデリン・ファン・オルデンボルフ
1962年オランダ・ロッテルダム生まれ、ドイツ・ベルリン在住。
近年、第57回ヴェネチア・ビエンナーレのオランダ館をはじめ、東京都現代美術館(日本、2022/23)、ウッチ美術館(ポーランド、2021年)、ドス・デ・マヨ・アートセンター(スペイン、2019-2021年)、daadgalerie(ドイツ、2017年)などで個展を開催したほか、ソンズビーク20->24(オランダ、2021年)、シカゴ建築ビエンナーレ(アメリカ、2019年)、世界文化の家(ドイツ、2019年)、シンガポール・ビエンナーレ(シンガポール、2019年)、あいちトリエンナーレ(日本、2016年)、キーウ・ビエンナーレ(ウクライナ、2015年)など多数の国際展に参加している。