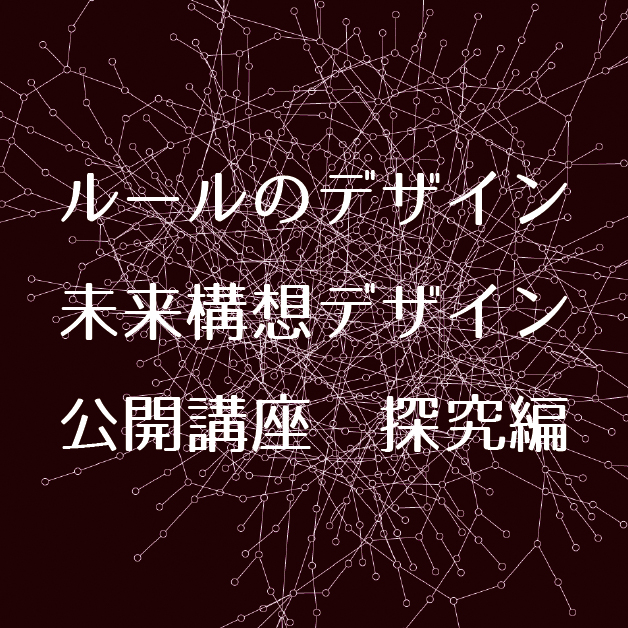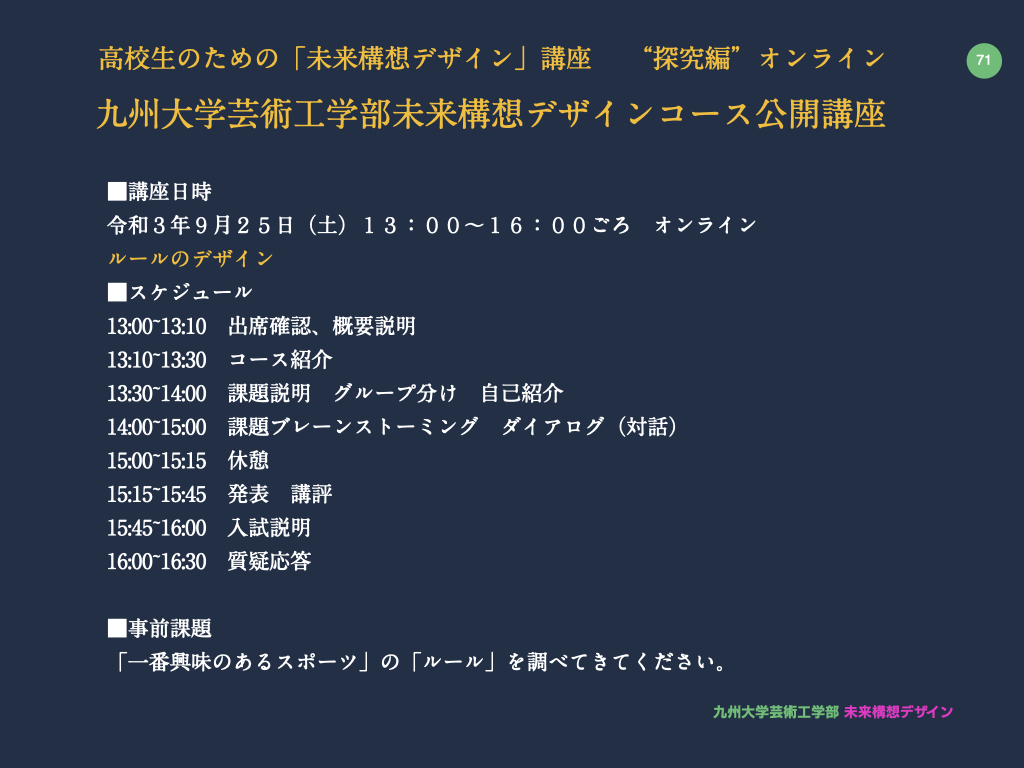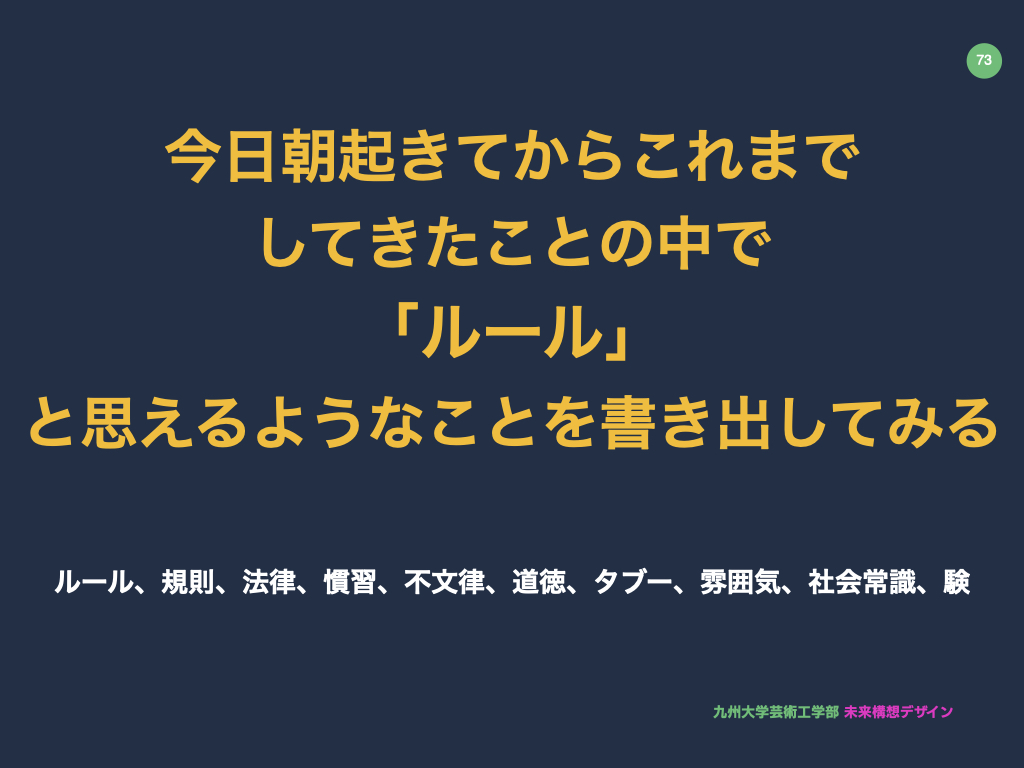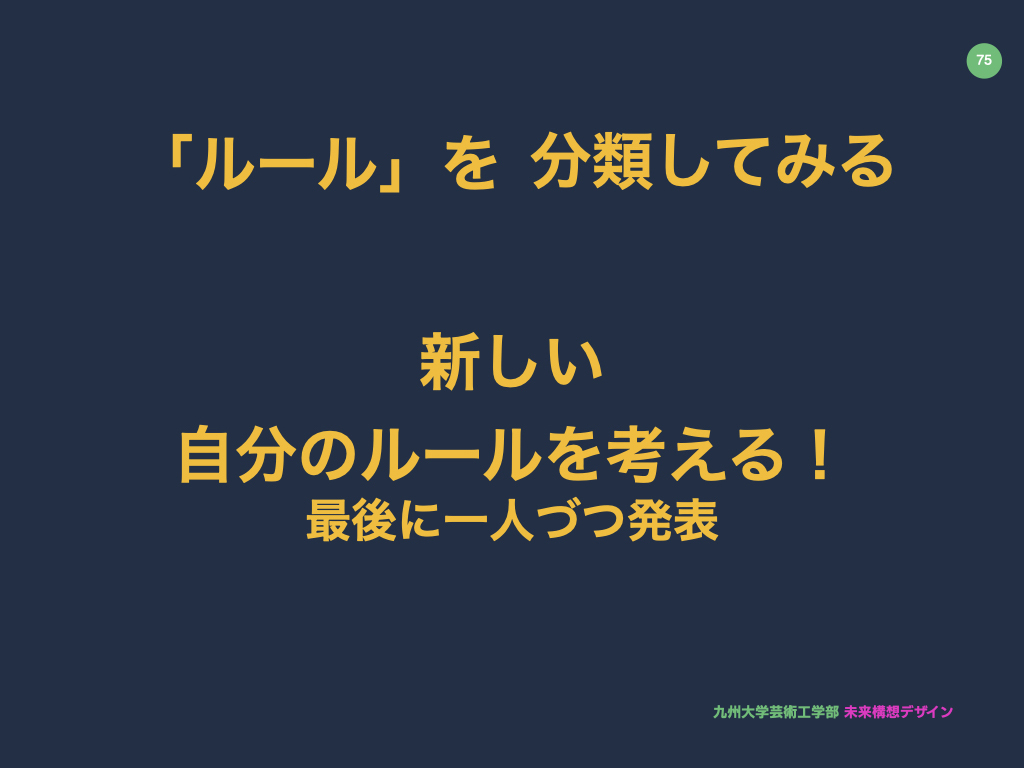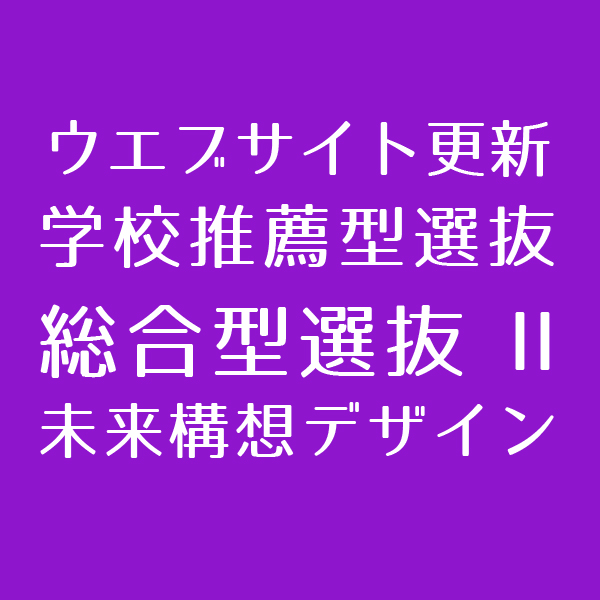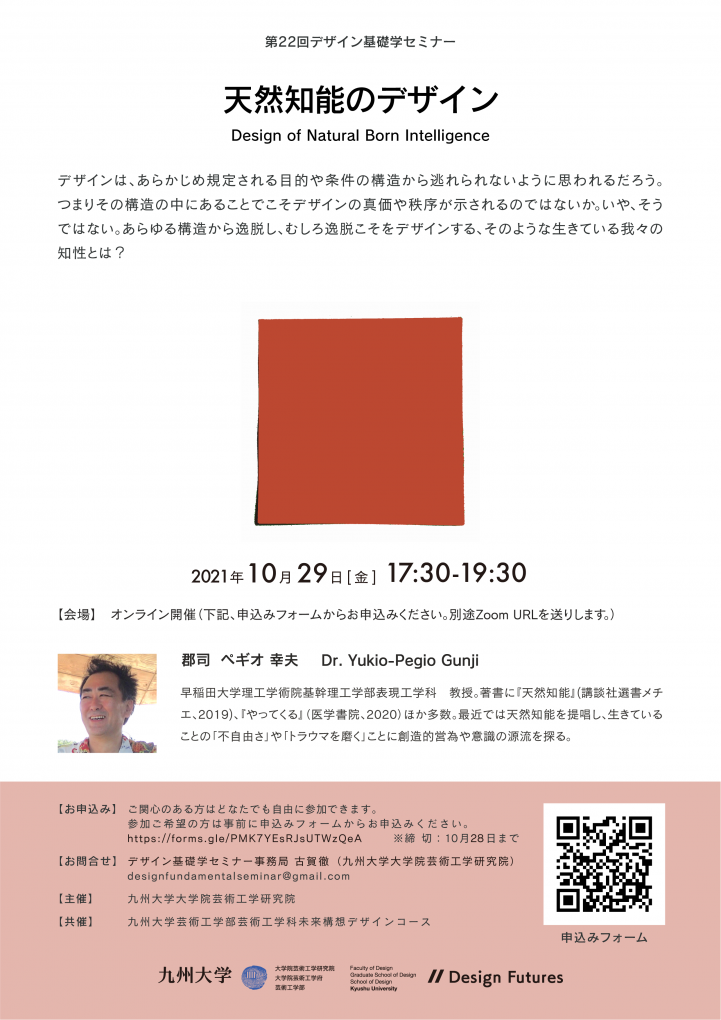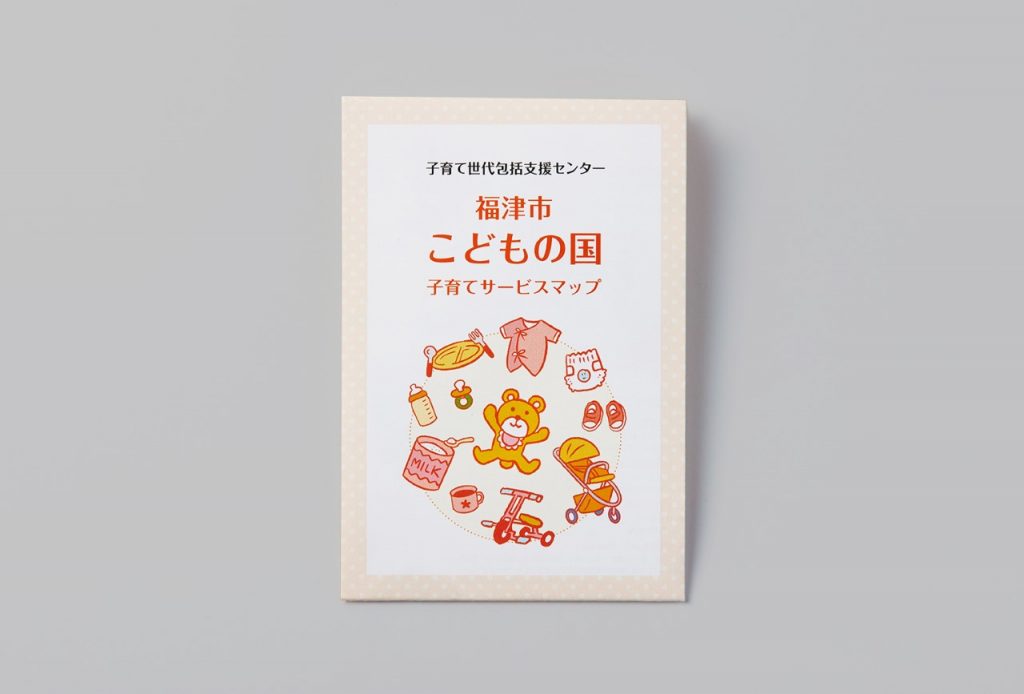九州大学 大学院芸術工学府、ビジネス・スクール(QBS)、ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター(QREC)は三部局が共同して、デザインとビジネスを融合する新しい教育プログラムの開発を目指してさまざまな取組を行っています。
デザインとビジネスはどのように繋がっているのか、そこで知的財産はどのような役割を果たしているのか、デザインとビジネスと知的財産を総合的に把握することで、デザインを用いたビジネスの現実が見えてきます。
2021年7月15日に開催した「デザイン×ビジネス×知的財産を考える」オンラインセミナーでは、三菱電機統合デザイン研究所でデザイナーとして活躍されている藤ヶ谷友輔さんをお招きし、インハウスデザイナーの視点からデザイン×ビジネス×知的財産の現状をお話しいただきました。
また、藤ヶ谷さんは個人デザイナーとしても活躍されており、個人デザイナーとしての視点からもデザイン×ビジネス×知的財産についてお話しいただくことで、企業におけるデザイン×ビジネス×知的財産とは違った視点も見出すことも目的としました。
本セミナーでは、企業におけるインハウスデザイナーが考えるべきことは非常に多角的であり、コスト、ニーズ、流行、地域的特性などを総合考慮した上で実際のデザインに落とし込み、その周辺まで含めて知的財産権を取得すること、個人デザイナーとしては自身が創作したいデザインを創作しつつも実際にニーズがあるか不明なため全てに知的財産権を取得することは現実的には困難であることなどが報告されました。
企業と個人の両方で活躍する藤ヶ谷さんならではの経験から、デザイン創作においても考えるべきことは非常に多岐にわたるということが明らかにされました。
知的財産、デザイン×ビジネス×アントレプレナーシップを融合した教育に関心のある学生や社会人の方々、企業や団体のみなさまに、ぜひご覧いただけますと幸いです。